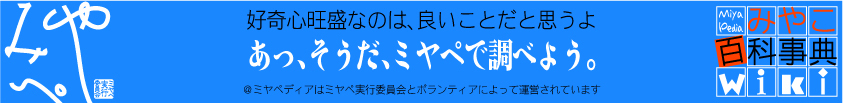鍬ヶ崎大正物語VOL3
目次 |
芸者・才八のアルバムから、華やかだった鍬ヶ崎花柳界を懐かしむ
~姉妹芸者・小竜・才八編~
芸者・小竜と、ひとつ違いの妹、才八の姉妹芸者の足跡を中心に、未発表の写真を加えて当時の鍬ヶ崎を偲ぶリメイク版VOL3として紹介する。また、今回はこれまでの芸妓関連の特集では触れてこなかった鍬ヶ崎芸者たちが出会った「盛岡芸者」のこと、鍬ヶ崎上町にあった雑貨商に残された「萬覚書帖」も併せて紹介する。
姉妹芸者・小竜と才八
夜が白むまで明かりの消えない鍬ヶ崎上町が花街であった大正末期、鍬ヶ崎花柳界にひとつ違いの姉妹芸者がいた。姉の名は「小竜」、妹は「才八」という。
小竜こと小瀬川トミさん、才八こと小瀬川トキさんは幼い頃から遊芸師匠につき芸事を習い、姉、小竜は大正10年に、妹、才八は翌年の同11年に半玉として初座敷を踏んでいる。
姉妹芸者・小竜、才八のことを知る人は今となっては少ないが、あっさりした性格の才八に、気さくな小竜は芸者仲間たちが見ても本当に仲の良い姉妹で、小竜が三味線、才八がそれに合わせて踊るという組み合わせが多かったという。小竜、才八が一本芸者として現役だった当時、半玉だったという春千代(澤口ハル)さん、万平(黒田エツ)さんたちにその印象を聞いてみると「小竜姉さんの三味線はほんとうに上手でした。芸には厳しい人で後輩に稽古をつけるときなど妹の才八さんでも本当に厳しくする人でした」と語る。また「二人ともめっぽう酒が強く、特に姉の小竜さんはお座敷が終わってから料理屋で飲んでいることもありました」と当時の小竜、才八の思い出を話してくれた。(昭和63年取材)
芸者たちの暮らし
鍬ヶ崎花柳界が最も隆盛を極めたとされる大正時代、売れっ子芸者ともなると一晩のお座敷の数も多く、月に70円~80円を稼いだ。この頃、郡役所お役人の給料が約50円程度であった。そんな稼ぎ頭の芸者を育てるため、里親になった料亭、料理屋、廓の店主たちは芸事習い事の投資を惜しまなかった。しかし、一人前として一本立ちした芸者は高給取りであったが、本人が手にした稼ぎは衣装代、化粧代、髪結い代、さまざまな付き合いなどでほとんど手に残らなかったという。
上町の芸者たちは里親の店、あるいは上の山寺周辺に居を構えていた。夜が白むまでお座敷があるのが普通だった芸者の朝はかなり遅く、午前8時~10時頃に起き出し夕方まで三味線や踊りの稽古に専念するのが日常だった。上の山寺周辺では午後になると誰かが小唄や端唄に合わせて三味線を爪弾く音が聞こえたりする花街特有の風情があった。
お座敷は昼の場合もあったが、ほとんどは夜になってからであり、食事と風呂を済ませ、浴衣を衣装に着替え、化粧、髪結いを終えて、芸者たちは箱番が割り符振ったお座敷へ向かった。
いくつものお座敷で踊る半玉
半玉(はんぎょく)は芸者になる前の修行中の少女のことをさす。「半」は半分、「玉」は女を意味する。これに対して一人前の芸者は、「一本」と呼ばれる。半玉は芸も半人前とされ、線香代(料金の俗称)も一本芸者の半分だった。半玉はきらびやかな振り袖に箱帯という鍬ヶ崎独特の帯の結び方をし、髪には簪をたくさんつけており、お座敷では一本芸者が弾く三味線や唄にあわせて舞い踊るのが仕事だ。いくつものお座敷で踊るため半玉の足袋はすぐに汚れる。そのため半玉たちは替えの足袋を持参し、巾着袋に入れて持ち歩いた。
お座敷でのお酒
大正時代の鍬ヶ崎のお座敷では日本酒が主流。当時ハイカラとされたビールも人気だった。ウイスキーもあったがお座敷で飲まれることはほとんどなかったという。
当時は現在のような厳しい風営法はなかったが、騒音公害のため三味線太鼓などの鳴り物は午前零時までという決まりがあった。それでもお座敷には時間制限はなかったため、客たちは芸者、半玉を交えて朝まで飲み明かすというのはそう珍しいことではなかったようだ。
鍬ヶ崎芸者の十八番芸・大漁踊り
鍬ヶ崎芸者の十八番芸はなんといっても「大漁踊り」だ。この踊りがいつから鍬ヶ崎花柳界で唄われてきたかは定かではないが、明治末期に鍬ヶ崎遊芸組合が販売したポストカードには、大漁踊りの恰好をした芸妓たちの姿があることから、明治末には大漁踊りが芸者衆の十八番になっていたことが伺える。
大漁踊りは定置網の男達が掛け声にあわせて網をひいたリズムで、基本的には浜の作業唄が元になっている。一説によれば遊芸師匠がそのリズムに新たな歌詞や踊りを振り付けたものとされるものと、歌詞そのものは宮古以南から宮古漁場へ働きにきていた人たちによるものという説がある。宮古浦での建網の創始は文政8年(1825)に船越村の田代覚左衛門が月山下の「鬼形」に設置したのがはじまりだ。鍬ヶ崎沖漁船頭、漁師たちに拒絶されたが、南部藩に申請し文政10年(1827)小舌網、地引網で開設した記録が残る。その後田代氏の功績により建網は発達し、この頃に「大漁唄い込み」も生まれたと思われる。
芸者衆の踊る大漁踊りは元歌の大漁うたい込みをアレンジしたもので、祝いの席では必ずと言っていいほど踊られた。踊り手となる芸者たちは別室で大漁踊りの衣装に着替え、腰に「ゴモ前掛け」手に「櫂」、船頭役が「振り樽」を持って登場する。お囃子は三味線、太鼓、唄の鳴り物が最低3人で、踊り手を加え7人~10人ほどの出し物となる。
大漁踊りは昭和26年、コロムビアレコードから発売された「三陸観光音頭」のB面に収録された。唄に鍬ヶ崎芸たちが参加し、唄を豊子、三味線が小竜と遊芸師匠の五条文代、太鼓が年子、お囃子が時子というメンバーで録音されている。この時レコードの録音時間に合わせるためかなりの部分の歌詞がカットされ約3分におさめられたという。また、翌年には毎日新聞社主催の「観光百選巡り」が東京で催され、鍬ヶ崎芸者たちは日比谷公会堂で大漁踊りと「かまどけぇす」を披露している。大漁の縁起担ぎと、芸者たちのお色気たっぷりな踊りは大喝采を浴びたという。
特別付録 盛岡の花街八幡と本町
江戸の浄瑠璃語りの芸人・富本繁太夫が東北を旅した時に記した旅日記『筆満可勢』によると、文政11年頃(1828~)一行が盛岡城下で興業している時に、志家町の遊郭で遊女から宮古の話を聞いたことが記されている。これが女衒(ぜげん・田舎から少女を買い集め遊郭に斡旋する生業の人)などによって宮古から売られた少女が盛岡の遊郭にいたものか、この頃すでに宮古から盛岡へ遊女や芸者が出稼ぎに出ていたかは確定しないが、明治頃には宮古の芸者が盛岡へ出稼ぎに出ていたらしい。ただし、出稼ぎ先となる花街は、本町であり、盛岡でも格式が高く伝統を重視した八幡町のお座敷に出るということはなかったという。
八幡町は盛岡城から東に延びた通りで、江戸初期に南部氏が盛岡城を築城後、八幡信仰を庶民に開放するため建立した盛岡八幡宮の門前にひらけた町だ。この神社は多くの参拝者を集め、同時に神社へ至る通りは門前町として旅籠や遊郭が発生したものと考えられる。道中日記『筆満可勢』の著者富本繁太夫によれば「当八幡町に茶屋あまたあり。所生まれの娘を芸者に出し、八、九人いる」と記している。本町通りは盛岡城から北に向かって延びた、下の橋から現在の四ッ谷教会に至る通りで、八幡町より歴史は浅いが江戸期から明治を経て戦後の昭和40年頃までそれぞれ賑わった盛岡を代表する花街でもある。
花柳界は特殊なしきたりや約束事の多い世界だが、その文化はひとつの町で発生し完結する場合が多い。それは芸妓たちの髪型、着付け、帯の巻き方にはじまり、三味線の弾き方、踊りの作法などなど、どれをとっても鍬ヶ崎には鍬ヶ崎の、八幡には八幡の「型」というのがあった。それは芸妓達の「粋」な部分であり同時に「印」でもあった。そのため古い写真に写った芸妓の着付けひとつとっても、これは鍬ヶ崎芸妓ではないと判ってしまうのである。
鍬ヶ崎芸者が八幡のお座敷へ出ることはほとんどないが、八幡の芸者が宮古のお座敷に来ることはよくあった。これは盛岡の旦那衆が芸者を連れて宮古を遊興する際に連れてきたもので、昭和初期頃には浄土ヶ浜にあったお座敷で旦那衆や芸者衆を囲み盛岡の話をきくことがよくあったという。とかく格式の高い八幡では、本町が仙台の遊芸師匠を招くと、八幡は東京の遊芸師匠を招くなど、とかく地域一番の格式を誇示する傾向が強かったという。これは八幡を利用する旦那衆に対しての威厳でもあり、最高の芸妓を育て、最高の料理で、最高の旦那衆を楽しませるという図式だった。当然ながら八幡を利用する客は政治家、役人、投資家などが多く、料金的にもかなり割高であった。