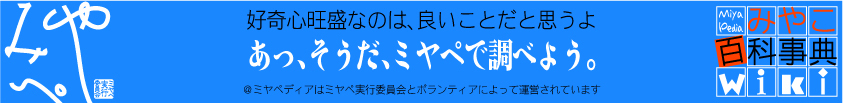鍬ヶ崎哀歌VOL2
目次 |
芸者・花香
明治に生まれ、鍬ヶ崎花柳界も隆盛を極めた大正時代に売れっ子としてその名を残したのが芸者「花香」であった。
花香は子供の頃に上町にあった宮喜楼に身を寄せ、当時の芸妓がそうであったように十五歳で半玉に、十八歳で一本立ちした。花香の均整のとれた顔立ちは半玉時代から人気で、一本立ちするとたちまち鍬ヶ崎一の人気芸者となったという。
- 花のように香りたつ女の色香…。という意味であったか。
- 芸者花香は鍬ヶ崎で青春時代を過ごし、そして女になっていった。
- 大きな瞳と均整のとれたその面影は現代でも美人として通用するだろう。
- 澄まし顔でカメラに向かうその仕草は半玉時代から変わらない。
- 一本立ちし、一人前の芸者として鍬ヶ崎花柳界にその名を響かせたという花香は
- 時代が激動の昭和に入るとともにいつしか消えてしまうのだった。
高台の小さな料理屋たいら松のこと
花香が売れっ子だった時代、鍬ヶ崎上町の高台、ちょうど上ノ山(常安寺分院)からさらに山手に登った場所に、客間が二つ程度のこぢんまりした料理屋があった。高台からは鍬ヶ崎の港と月山が一望でき、崖に沿って大きく枝を伸ばしたアカマツの巨木があった。この小さな料理屋の名前は「たいら松」と呼ばれ、夏保峠、道又沢、上ノ山から続く小道の交差点にあたることから、景色と宴会を楽しむというより、旦那衆とひいきの芸者衆がこっそり逢う隠れ家のような料理屋だったという。たいら松が営業していた時代は明治末期から大正はじめ頃と考えられ、営業年数は極めて短かったと思われる。
花香のアルバムにはたいら松でひきの旦那集らとビールを飲む写真があり、明治末期から大正時代には鍬ヶ崎でビールが飲まれていたことがわかる。当時のお座敷で飲まれたものは燗酒がほとんどであり、時代が下るにつれてからビールやウイスキーなどが登場している。
芸妓の舞台・有楽座
旭屋、開清庵、玉川、新玉川などの料理屋が軒を並べていた上ノ山(現・常安寺分院)へ向かう坂道を下ると、上町のメイン通りに出た。そこから路地を通り海岸へ向かった先に有楽座という小さな芝居小屋があった。隣には鍬ヶ崎遊芸組合の事務所があって、路地をはさんで梅香、丸福旅館、沼崎商店があり、その隣が相馬屋であった。
有楽座では芸妓たちの発表会をはじめ、晩年には活動映画を上映。また、稲荷神社、金比羅神社、熊野神社の祭りには旅芸人の芝居や、義太夫、長唄などの見世物興行もさかんに行われた。また、有楽座入り口に掲げられた看板の周りには鍬ヶ崎芸妓の名前の札が当時の芸者番付に習って並んでいた。
厳しい半玉の修行と発表会
15歳で半玉にあがるのが一般的であったが、少女たちは幼い頃から芸に励んだ。少女たちを引き取った里親たちは共同で踊りや三味線などの師匠を盛岡などから呼び寄せ、少女たちに習わせた。また、年輩芸者が礼儀作法やお座敷でのエチケットなどを教えるとともに唄や踊りも教えた。遊びたい盛りの少女たちにとってスパルタ教育で仕込まれるそれらの修行は時には苛酷なものだったという。お座敷での畳の歩き方、お辞儀の仕方、歩き方など、時には棒で叩かれ、礼儀作法を覚えたという。
大正鍬ヶ崎世相覚書
大正時代に全盛を迎えた鍬ヶ崎上町には多くの料理屋と遊郭が軒を並べていた。そのほとんどが芸妓を呼んで宴会を楽しむと同時に、遊郭としての顔をもっているのが普通だった。そのため料理屋でありながら遊女たちが張見世をする場所があり、遊女部屋や廻し部屋があった。ただし遊女たちは芸妓のように上町界隈のさまざまな料理屋の宴会に出向くのではなく、定められた郭での張見世しかできなかった。
そんな料理屋にも「格」があったようで、格の高いとされた相馬屋、旭屋はそれなりの設備と贅沢な調度品を揃え、一流の板前が包丁をふるって凝った料理でもてなした。両店を比べると甲乙つけがたいが、歴史が古いのは「相馬屋」で、港に向かった部屋にはバルコニー付きの座敷や、当時ハイカラとされたビリヤードの台なども備えていた。一方「旭屋」は和風三階建で、鍬ヶ崎一の広い大きな宴会場をもっていた。この二店は当然ながら他の料理屋に比べて料金も割高だったがそれなりの階級の人々に愛されたという。
時代が下り、若者たちが宴会に繰り出したというのは福井、開清庵など比較的低料金で楽しめる料理屋が使われたが、それさえも年に数回の贅沢であり、現代のように気軽に「飲む」という感覚とは違っていた。
お座敷作法
当時のお座敷における順序を記しておこう。
客はお座敷に通され好みの芸妓を指名する(番付表のようなものがあった)例えば芸者二人に半玉二人…。当然芸者一人の場合もあるし、呼ばない場合もある。
料理は最初に「通し」がでる。通しは果物と決まっており、りんごやぶどうなど、季節の物が出された。
次いで料理が出る。料理は料理屋の格によってさまざまだが、刺身や茶碗蒸し、秋には松茸の土瓶蒸しなどが出されることもあった。
芸者は指名が「掛る」(掛ける、掛るで指名を意味した)と箱番(検番とも言う)で伝票をもらい、指定された料理屋へ出向く。料理屋の帳場で主人に挨拶をして伝票を渡し、指定されたお座敷へ上がる。三味線は箱番の係員が頃合を見てお座敷へ運んだ。
芸者はお座敷の入口で客に挨拶し、客にお酌をして場をもたせる。そして頃合をみて三味線を出してもよいかと客の許可をもらい三味線を弾く。唄は芸者が唄う場合もあるし、客に「あれを弾け」と指示され客が唄う場合もある。唄と三味線に合わせて半玉たちが踊り、場を明るくさせる。
半玉たちは色々なお座敷で踊るためすぐに足袋が汚れた。そのため半玉たちはきんちゃく袋に替えの足袋を持ち、お座敷に上がるごとに取り替えたという。
宴会が終わり客が帰ると芸者は帳場へ行きお座敷での時間を記載した伝票を受取り箱番へ提出した。
芸者が客を上町の外れまで見送る場合もよくあった。送り先は古くは夏保峠、昭和になると光岸地の切り通しまでだった。料理屋を出てそこまで歩く僅かな時間は、芸者たちが客との次の約束を取り付けたりする貴重な時間でもあった。
客は馴染みの芸者を通して呼ぶタイプと、積極的に新人に「掛ける」タイプがあった。芸者たちも客を自分に引き止めたかったから、甘く色っぽい声で客を惑わした。時には誰かが誰かのお客を取ったとか取られた…といういざこざもあったが、それもまた花街の一興であった。
時代の波に消えた幻の花街
現在のように鉄道や陸路が整備されていなかった明治・大正時代、宮古町へ入るには海路が主体だったため鍬ヶ崎が宮古の玄関口であった。当時航路をもっていたのは明治30年頃に不定期就航していた東京湾汽船株式会社で、同社の独占であったが、明治40年代に入り、釜石の資本家を中心に岩手県沿岸町村の地元資本により「三陸汽船株式会社」が発足、鍬ヶ崎からは宮古~塩釜の三陸定期汽船が就航した。これにより明治末期から大正にかけて、鍬ヶ崎は新たな物流基地として発達しはじめたのである。
古くから港町として栄えた鍬ヶ崎だが、大型船により人と物が行き交うようになると、花街も比例するように賑やかさを増しながら花柳界は新しい文化を吸収しはじめる。建網にはマグロが入り、網元は何を疑うことなく大漁に歓喜した。魚を買いつけるため外部からも大勢の人が鍬ヶ崎に入り市場はごったがえすと同時に、夜は大勢の客が花街へ繰り出した…。そんな浮世の中、多くの芸妓たちが花を咲かせ散っていった。
戦後、混乱の時代を経て、花街鍬ヶ崎は蘇ると誰もが信じていた。しかし、花街は遠い幻のごとく消え去ったまま戻ってはこなかった。それは戦後の物資不足、教育制度の改革、女性の権利を守る戦後の民主主義などと言われるが、何のことはない、民衆の遊びや娯楽が早くて簡単で安価なものへと移行したためである。
アイオン台風で分断された山田線が復旧し、物流は海路から鉄路へと変化した。同時に人の流れも西へ、西へと移動してゆく…。かつて釧路から東京へ向かう途中、船で鍬ヶ崎に立ち寄った石川啄木は「白粉の匂いが漂う花街」と啄木日記に記しているが、現在の鍬ヶ崎にはその面影すらもうどこにも残っていない。遊里鍬ヶ崎はその栄華を知るごく少数の老人と、手元に残された数少ない写真の中にしか見ることができない。