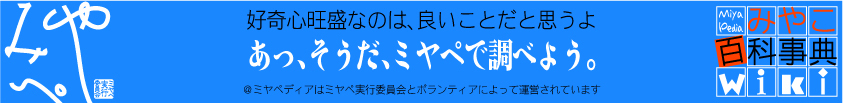2008/03 遊里語は宮古弁の基本テイストだ
その昔、港町だった鍬ヶ崎には大規模な廓街があり南部領内でも有数の遊里であったのは紛れもない事実だ。資料的には江戸中期の南部藩士が記した『栗拾日記』によると町家300軒のうち遊女160人許と記載されており、いくらなんでも「アンマリゲー/あまりにもやりすぎ」だが、そう誇張してしまうほどその当時の鍬ヶ崎には遊女や芸者のたぐいが「ノッコライェード/多量に・わんさか」いたと思われる。そんな江戸時代末の文政11年(1828)江戸から浄瑠璃師匠として鍬ヶ崎へ入ったという繁太夫という芸人が記した『筆満可勢』という旅日記によれば、滞在中宮古町の町医者へ通い持病の梅毒の治療をしたこと、「ヒックミ/仲間」の三味線弾きに持ち金を「カッパラーレデ/盗まれて」目明かしに探索願いを出したこと、宮古を発つ前日お得意様から土産にと禁制の「イリコ/干し海鼠」や干鮑を「モダサレダー/土産に貰った」こと、「小菱屋」という遊女屋で「おくら」という女と交わり床でその女が「エンヅク、エンヅク」と叫んだことまで事細かに記載されている。ちなみに「エンヅク」は「エンヅイ/具合が良くない・居所が悪い」という宮古弁だが、繁太夫には「エンヅク」と聞こえたのだろう。
そんなわけで港町として栄えた鍬ヶ崎の側面には江戸の頃から花街・色町としての伝統文化が受け継がれてきた。それは三陸定期汽船就航とともに明治大正を経て最大に開花し、太平洋戦争とその敗戦を経て「サピケナガラ/衰退しながら」戦後の売春禁止法が制定される昭和33年まで脈々と受け継がれてきた。しかし現在、最終的に花街として栄えた鍬ヶ崎上町界隈を訪ねても遊郭らしき面影を持つ建物は「ワツカ/僅か」しかなく、この通りに紅色の「ボンボツッコ/ぼんぼり」や「チョウツン/提灯」が揺れ、揚屋の張見世に女郎がはべっていたのを想像することはできない。全ては時の彼方に流れ去り鍬ヶ崎全盛時代の文化は忘却したかと思える。が、しかし、遊女が消え、芸者の姐さんたちのほとんどが彼岸へ旅立った今でも、遊郭で使われた特殊な遊里語が宮古弁として残っているのである。前出の浄瑠璃太夫が遭遇した「エンヅク」も遊里言葉であり、その後に「エンヅイ」と変化して宮古弁として定着したとも考えられるのである。
遊里語とは悪所とされる岡場所で使われる隠語であり風俗系の商売用語だ。地方から買い集めた女を囲っている遊郭経営者は女達が使う言葉を統一して店の「型」や「格」を固定したという。これは江戸吉原などで使われる「~デアリンス/~であります」のように、この言葉を使うことで客に対して吉原という非日常空間を意識させ同時に、遊女の言葉から予測される地方色を消すことにより客と遊女の土地的感情をも消すことができたと考えられる。江戸時代の風俗ルポライターでもある『好色一代男』で有名な井原西鶴によると、上方の揚屋では各店により独特な隠語が使われそれがひとつの「粋」になっていたと記述があるほどだ。そんな流れの中、鍬ヶ崎でも他所の遊郭に習い遊里言葉が使われていたであろう。とは言え、上方のように鍬ヶ崎独自の言葉というものは存在せず吉原でも使われた語尾に「~ンス(アリンス)」を付けた言葉として派生したと考えられる。これが最も如実なものに「シャンス」や「~シャンセ」がある。「シャンス」は「ザンス」に変化し最終形で「ゴザンス」になる。「~シャンセ」は「~センセ、~サンセ」に変化して最終的に「クタセ(サ)ンセ/ください」などの敬語的日常語になる。また「シャンス」は「ナンス」に変化して最終形で「ネンス」へとも変化する。これは完全に宮古弁で使われる「アノネンス/あのね」、「ソウダガネンス/そうですね」へとつながっている。究極的に言うと、鍬ヶ崎に遊里が発生する以前の江戸前期あたりまで宮古弁には「ネンス」や「ゴザンス」はなかったとも推測される。
ではどうして遊里語が色町から流出するのだろうか。おそらく遊郭へ出入りする業者、身請けされ商店などの後妻や「オナメサン/妾さん」となった芸者、そして廓へ通う客たちによって言葉が廓の外へ持ち出されたのであろう。これは会話の中に特殊な空間で使われる隠語を使うことでその言葉を語る人のステイタスが一般人より高い粋な人に見える錯覚からである。このような現象は鍬ヶ崎港に入る上方の船の乗組員の言葉を真似て「オオキニ/ありがとう」と使った宮古の洒落人や、現在のタレントや芸人がテレビの中で使う言葉を真似て会話する若い人たちと同等である。人は新しい言葉や耳触りの良い言葉に敏感で、その意味を知りたがり、同時にその言葉を自分も使って流行を体感するのである。
遊里語が巷に流れる現象は鍬ヶ崎をベースとした宮古弁だけではないだろう。これはまだ私論の域だか、盛岡弁として有名な「ナハン」も見方によれば八幡町あたりの花街から派生した言葉とも考えられる。「ナハン」の使用例は「ンダ、ナハ、ン/そうですね」であり語尾の「ン」が強ければ強いほど女言葉になる。これに同等に当てはまる宮古弁は「ソンダガネー/そうだね」とか「ホンダガネー/本当だね」あたりだ。これらの先頭語を省き「ン」からスタートし「ンダナ」で「そうだな」、「ハ」と「ン」で言葉の伸ばし「ー」を意味する。宮古弁の「ハーイグビス/もう行こうよ」で使われる「ハー」こそ「ナハン」の「ハン」部分なのかも知れない。 僕が高校生だった頃、中卒で盛岡の工務店に就職した友人が盆休みに帰ってきて、颯爽と大型バイクに跨って僕の家に遊びに来た。ちょっとあか抜けした彼にいっぱいゼニを稼いでるのか?と僕が聞くと彼は一呼吸おいて「…んだなはん」と答えた。「ナハン」との初遭遇は宮古から盛岡へ出た盛岡かぶれの宮古人だった。
懐かしい宮古風俗辞典
【あづぎばっとう】
薄く溶かした甘いコシあんのタレにきしめんのようなひもかわうどんを入れて食べる甘い麺料理。発生と名前の由来は諸説ある。
「ハットウ」はそば粉や小麦粉を練って作った料理の「ホウトウ」の訛ったものらしい。この食べ物の出所は山梨、長野あたりらしく南部の殿様が甲斐の国からきた人なので岩手に伝搬されたという説もある。しかしながら当時の岩手県では小麦はごく僅かしか栽培されていなかったから、現在のひもかわうどんのような形で伝わったというのは無理がある。きっと南部領ではそばの粉を使う調理法の方が主になっていたはずであり、そば粉を熱湯で練ってそれをちぎってそばに入れる「ヒッツミ」と「ソバカッケ」が混ざったようなものが原型と思われる。また、甘みに使われているアズキが高級品だったためそれを使った料理が一般家庭では禁止されており、そのことから「御法度」が「ハットウ」になったという半ば強引なダジャレ的説もあるが、この説はあまりにもナンセンスなので最近は聞かれなくなった。
現在はいつでも食べられる「アズギバットウ」だが、本来「ハットウ」は夏の食べ物で、「ナノガビ/8月7日」に一斉に行われた「イドソーズ/井戸掃除」「ハガハレー/墓掃除」に伴って「七回水を浴びて、八回はっとうを食べれば風邪をひかない」という俗信があった。これは水が腐りやすい夏の生活の知恵であり、食中毒などを防止する慣例だったのだろう。