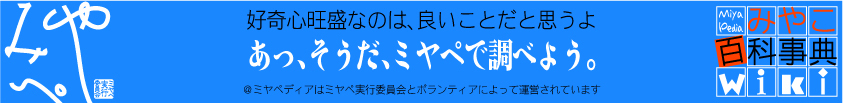黒森神社
黒森神社の祭神は、須佐之雄命、大巳貴命、稲田姫命である。神社の社殿は、嘉永3年(1850)に再興されたものだが、江戸時代の資料には、建久元年(1190)の棟札があったという記録が残されている。現存するものでは、建武元年(1334)の鉄鉢、応安3年(1370)の棟札があり、この当時あるいはそれ以前から黒森神社(黒森大権現)の信仰があったといわれている。社殿は、平成2年(1990)7月に市の有形文化財(建造物)に指定されている。社殿の奥には御祖父杉、御祖母杉という杉の老樹がある。御祖父杉は枯死しているが、平成2年(1990)10月の樹医の鑑定結果では、御祖母杉は6~7千年位、また境内の杉も千年位の樹齢とされている。また、黒森神楽と密接な関係があり、廻り神楽の舞い立ち(1月3日)は、黒森神社の社殿前で行われる。
- 【参考資料】宮古のあゆみ:宮古市(昭和49年3月)黒森神社パンフレット
目次 |
黒森神社に奉納された鉄鉢
建武の鉄鉢の名で岩手県指定文化財として指定されている直径約50センチほどの鉢。使用目的ははっきりしていないが、供物や賽銭を入れたものであろうと考えられている。銘は陽鋳(浮き出し文字)の逆文字で、南北朝期建武元年(1334北朝年号)となっている。
敬白
道徳
八月廿日
建武元年
黒森□
当山
癸戌
鉄鉢の年号の下に横書きされた干支十干の「癸戌(みずのといぬ)」には若干の疑問がある。年号的に見ると建武元年は癸戌ではなく「甲戌(きのえいぬ)」であり、しかも干支十干には「癸戌」というものは存在しない。このような初歩的間違いはどうして起きたのかは不明だが、おそらくこの鉄鉢が中央の仏師等の職人の手によるものではなく、中世初期から活発だった閉伊地方の製鉄によって作られたものであるため、法具や仏像を造る仏師のように干支や十干に詳しくない土着の鋳造師が制作したためであろうと考えられている。また、敬白に次ぐ「道徳」という文字は、人物名と考えられ、おそらくこの時代にはすでに存在していた黒森山の安泰寺の住職と考えられている。(小笠原康正氏所蔵)
南北朝期の黒森神楽獅子頭
黒森神社に古くから伝わる黒森神楽には、南北朝時代初期と推定されるものをはじめ、現在22頭の獅子頭がある。そのうち16頭は「ご隠居様」とされ大切に保管されているが、このように同じ神社の獅子頭が古い時代から現在まで揃っているというのは希であり、ご隠居様とされる獅子頭16頭は岩手県の文化財に指定されている。
黒森山拝殿峠の・安泰寺梵鐘の拓本
黒森山には山腹の黒森神社を庇護するかのように安泰寺、赤竜寺という二つの密教寺院があったとされる。(両寺院とも廃寺となり現存しない)このうち赤竜寺建立は比較的新しいが、一方の安泰寺は創建が南北朝期ではないかと考えられている。安泰寺があった正確な場所は定かではないが、安泰寺の梵鐘の文字によると貞治四年(1365北朝年号)があり、南北朝中期には安泰寺が黒森山にあったことを意味している。鐘には次のような銘が独特の書体で陽鋳(浮き出し文字)で現されている。
敬白 うやまいもうす
釈迦納安泰寺推鐘 しゃかのうあんたいじすいしょう
長一尺八寸口一尺六寸 ながさいっしゃくはっすんくちいっしゃくろくすん
右之鐘者天長地久 みぎのかねはてんちちょうきゅう
奉為殊禅衆 ことぜんしゅうのためたてまつる
直阿走門惣百姓 ちょくあそうもんそうひゃくしょう
結衆尽法界衆生 しゅうじんほうかいしじょうをむすぶ
平等利益儀也 びょうどうりやくのぎなり
大旦那式部太夫源長時 だいだんなしきぶたゆうみなもとのながとき
別当 べっとう
仮海 かかい
勧請主 かんじょうぬし
旦那恵心 だんなえいしん
貞治四年 乙巳十一月六日
この鐘は江戸末期鐘を保管していた宮古代官所が火災に遭い焼失、現在は拓本のみが残されている。また、この鐘を奉納した所以を書き残した古文書が山口小笠原家にあり、そちらにも貞治四年の北朝年号がある。同古文書によると寺は黒森神社の通称・拝殿峠にあったもで、鐘は里人の黒森入山を警告するものだったとされる。黒森神社は江戸時代以前から南部氏の信仰も厚かったため、里人の入山は固く禁じられていた。
黒森神社改築の棟札
鉄鉢が奉納された建武年間にはすでに存在していたと考えられる黒森神社には今から約600年前の南北朝時代の軒札が存在する。軒札には南北朝時代の南部家を知るためにも重要な、第12代南部藩主である三戸南部伊予守・信長(のぶなが)の名もある。所々判読できない文字もあるが概ね次の文が記されている。
参封 さいふう
我適曽供養今復遷親近 われまさにかつてくようしいままたしんきんにせんず
当郡 地頭南部光禄 とうぐん じとうなんぶみつろく
旦那 沙弥宗光 だんな さやむねみつ
旦那 小笠原太郎三郎 だんなおがさわらたろうざぶろう
聖主天中天迦陵頻伽声 せいふてんちゅうてんかりょうひんかこえ
奉 たてまつる
造営治明御宇黒森山権現御社一宇 ぞうえいじめいおんうくろもりさんごんげんおんしゃいちう
哀愍衆生者我等今敬礼 あいびんしゅうじょうわれらいまけいれい
南部伊予守信長 なんぶいよのかみのぶなが
旦那 沙弥真清 だんな さやしんせい
旦那 対馬房阿闍梨明春 だんな つしまぼうあじゃりめいしゅん
旦那 (10名略)
大工 三郎左衛門
執事 治郎房律師宗清 じろうぼうりつしむねきよ
応安三季 おうあんさんき 歳次庚戌 さいじかのえいぬ 十二月十七日
河原田右京助道 かわらだうきょうすけみち
小工 五郎太郎重光 しょうく ごろうたろうしげみつ
この棟札にある信長は、応安年間の32年前に没していることから、後の第12代藩主政行が黒森神社を造営し父の名をかりて北朝年号で印したものと考えられている。
南部氏は甲斐源氏の一族で、鎌倉幕府草創期に光行(みつゆき)が甲斐国巨摩(こま)郡南部郷(山梨県)を名字の地としたことに始まる。南部氏は後醍醐天皇と足利尊氏の対立が決定的となった建武2年(1335)、都を占領した尊氏を討伐するため南部師行(もろゆき)や葛西清貞(きよさだ)らを引き連れて京に進軍、北畠顕家の軍勢に加わり勝利する。しかし、鎮守(府)大将軍・顕家らと共に多賀城に戻ったころには、すでに奥州に不穏な動きがあり、尊氏の子・義詮(よしあきら)を補佐する鎌倉府執事の職にあった斯波家長(しばいえなが)が奥州総大将に任命されるとともに奥州には足利派に属する武士も増えてゆくことになる。
その後、顕家の弟・顕信(あきのぶ)が陸奥鎮守府将軍として陸奥に入り、南部師行の弟・政長(まさなが)、葛西、伊達らの武士とともに足利方の石塔義房(いしどうよしふさ)らと戦いを続ける。しかし、1342年(南朝・興国3・北朝・暦応4)ごろには足利方の優勢がほぼ固まり、1353年(正平8年・北朝・文和2)にはすべての拠点を失って顕信は逃亡し、奥州における南北朝の動乱はおさまることになる。
黒森神社・是津親王伝説とは
黒森顕彰会では南朝方として伊勢からこの地に流れたとされる『三上家文書』に残された記録や逸話はじめ、江戸期の漢学者・高橋子蹟(宮古・高橋家)による『黒森山稜記』、江戸初期に廃寺となった黒森山の安泰寺、江戸末期に廃寺となった赤竜寺の縁記を記した『長根寺文書』、現在の社下にあるとされる謎の石棺、棟札の調査などから、黒森神社の旧社殿跡の古黒森(こくろもり)を中心に黒森山が慶長天皇御陵であると唱え、多くの考察や論文、古文書写しなどを宮内庁に送った。 しかし、それら文書に登場する是津親王は垂仁天皇(第11代天皇・紀元前69~)の第5子ということで『黒森神社俗縁起』に登場するが、実際の皇史にその名は見あたらない。しかしながら伝説によれば、都落ちし奥州へ流れた親王は田鎖地区の屋敷に身を寄せていた(磯鶏説もあり)としている。ある日親王は飛鳥方浜(磯鶏)へ赴き、自身の不運を嘆き入水した。その後、家臣等は親王が磯鶏の飛鳥方浜へ行ったことを知り捜索するが亡骸を見つけることはできなかった。そこで親王が愛玩していた二羽の鶏を船に乗せて捜索すると洋上で鶏が啼いたためその近辺を捜索したところ遺体が発見されたと伝える。遺体は現在の藤原で火葬され、後に通夜と火葬をした地に藤原比古神社が建立されたという。火葬後の灰はこの地で最も高い山へ埋めよという指示から、家臣達は黒森山に登り親王の灰を祀り、御陵としたという。 この伝説は前述の黒森神社俗縁起とされる江戸時代の学者・高橋子蹟の『黒森山稜記』の中に登場する逸話だ。この伝説の時代尺度はとてつもなく古く、そのような時代に藤原比古神社、黒森神社等の信仰媒体、あるいは社のようなものがあったとは到底考えられない。また、親王が愛玩していたという鶏に関係した地名の起こりも、漢字すら一般化していない時代だけに安易に結びつけたのは、時代が下ってからの創作とも考えられる。
黒森の謎を追った黒森顕彰会の足跡
黒森神社の創建はいつの頃だったか正確には判っていない。現在の社は江戸末期に行われた三度目の遷宮によって建立されたものだ。黒森顕彰会ではその社の下部にある箱のようなものと、その下に築かれている石組みが石棺ではないか?と考えた。いにしえの時代、現境内下の丘陵地にある古黒森にあった社から、三度の遷宮と何度となく行われた改修等で遺骨は大切に保管され現社下に埋葬されていると推測したらしい。しかし最近になって現社の箱と石組みは当時の神社建築における意匠であるらしいと考えられている。だからと言ってその下には何もないのか?と言えば疑問だ。しかし、過去から現在に至り誰も黒森神社を発掘調査してはいないのだ。昭和初期に一大ムーブメントを巻き起こし黒森神社を徹底的に検証した黒森顕彰会でさえも、古文書や伝説だけを頼りに長慶天皇御陵説を打ち上げているが実際に大規模な発掘調査をしたわけではない。 黒森神社は社を持つ神社として、ひとつの霊山としていつの時代から信仰されたのかは判らないが、発掘をして何らかの遺物を探す以前に、今も昔も里人の信仰を集めてきた山であり、これからもそれを明確にする必要はあえてないのかも知れない。謎多き黒森山…。だからこそ幾多の伝説を生んできたのではないだろうか。
黒森山と義経北行伝説の謎
源平合戦の英雄から一転し、兄頼朝に追われる身となった源義経は、奥州藤原氏の庇護で平泉に匿われるものの、結果的には藤原秀衡亡き後の内紛と巧みで狡猾な頼朝の策略により、高舘にてその短い生涯を閉じた…。この史実は義経を襲った泰衡の飛脚が鎌倉で報告したものでそれを九条兼実が日記『玉葉』に記し、のち、鎌倉時代の公文書でもある『吾妻鏡』に記録された。これに対し泰衡は父、秀衡の遺言を守り義経を逃すため偽りの戦を仕立て、鎌倉に偽の報告をしたのではないか?と推測し、義経は衣川合戦以前に平泉を脱出していたのではないか?と唱えるのが義経北行伝説だ。この伝説の重要なポイントは次の通りだ。
●義経を誅討(ちゅうとう)を記した公文書『吾妻鏡』は義経の死後約80年後に記されたものであること
●『吾妻鏡』衣川合戦の詳細の元になった『玉葉』では義経が没した日、及びその最期の表現が違うこと
●手勢数十人の義経の居舘(高舘)を泰衡は約二万もの大軍で攻めたるという兵法の不可解さ
●討ち取った義経の首を鎌倉に送る日数がかかり過ぎており、義経の首実検が無理と思われること
●義経には影武者がいたと囁かれていたこと
●上閉伊、下閉伊に多くの義経伝説が残っていること
この他にも義経が密かに平泉を脱出して北行したのではないか…という伝説を固めるための事柄は多い。では、本当に義経は平泉で討たれず生き延びたと仮定した場合の歴史時系列はどうであろうか?。この謎に挑み、各地に散らばる義経北行伝説を集め時間軸に乗せ仮説として組み立てたのが、宮古の義経研究家・佐々木勝三氏の著書『義経は生きていた』なのである。これによると義経一党が平泉を脱出したのは文治4年(1188)4月半ばとされ、その月のうちに人首、五輪峠、物見山を経て気仙郡に入ったとしている。その4ヶ月後の8月には遠野、上閉伊を経て下閉伊郡大沢村(現・山田町大沢)に入り、9月には長沢村(現・宮古市長沢)に入り、その月のうちに黒森神社にて大般若経の写経をはじめていることになる。
影武者か偽戦か義経最期の謎
文治5年(1189)、義経を差し出さなければ奥州を征伐せざるをえないとの鎌倉からの通達が泰衡の元に届く。同年4月には義経を誅討せよとの宣旨が下り泰衡VS義経の衣川合戦となる。伝説の時系列ではこの時、義経は宮古の黒森山におり写経をしていることになる。では、衣川合戦において高舘で討たれたのはいったい誰だったのか?という疑問が発生する。この矛盾を埋め合わせるためには義経の影武者説、あるいは偽戦説が浮上する。義経影武者説には杉目太郎行信(すぎのめたろうゆきのぶ)という人物に関する伝説が語り継がれている。それによると杉目太郎行信は義経の従兄弟に当たり、年齢も義経と同等で容姿も似ていたといわれる。秀衡は早くからこの人物を義経の影武者として取り立て鎌倉の追究を逃れたという説もある。杉目太郎行信に関しては宮城県金成町の信楽寺跡にある小高い丘に石碑があり、碑文には「古塔泰衡霊場墓・文治五年・源祖義経神霊見替・杉目太郎行信碑・西塔弁慶衆徒霊・四月十七日」とある。碑の「見替」が「身代わり」をほのめかすことから、この人物が義経の影武者であったと推測されても不思議ではない。石碑は明治になってから建て替えられたものだが地元では昔からこの碑を義経の墓として、長い年月の間、何度も建て替えてきたというのだ。 義経北行伝説においては、この身代わり説、あるいは泰衡による偽戦がキーポイントで、杉目太郎行信といい、酒に漬けたとはいえ討ち取った義経の焼け首を約40日もかかり鎌倉に運んで首実検するという成り行きに不審を感じる。また、首実検では「運ばれてきたのが義経の首ならば相違いないだろう」という程度の検証であり、もはや判別がつかないほどに腐敗腐乱していたと考えられる首が本当に義経であったかは大きな疑問が残る。 結果的に頼朝は義経を泰衡が討ち取ったという報告と、それに伴う首実検の報告を得て、奥州藤原泰衡追討の宣旨を賜り、数ヶ月後には平泉を攻め落とす。泰衡は秋田方面へと遁走するものの、従者・河田次郎の裏切りで討たれ、裏切った河田次郎は泰衡の首を頼朝に届けるが、頼朝はこれを惨殺した。
佐々木勝三と高橋子績
義経研究家として義経平泉不死説を唱え、著書『義経は生きていた』『成吉思汗は源義経』(共著)で戦後の義経北行伝説のブームを巻き起こしたのは宮古市出身の佐々木勝三であった。勝三は明治28年(1895)宮古市横町に生まれ岩手県立水産学校を経て、大正6年(1917)岩手県師範学校第二部を卒業。明治大学商学部を経て、北米ワシントン大学に留学した。帰国後、明治大学商学部教諭となったが戦争で疎開のため郷里宮古に帰郷。戦後は宮古市進駐軍事務長、県立水産高校、宮古高校の教諭を歴任、勝三が編著者となって昭和39年に発行された『横山八幡宮記』編纂のため多くの郷土歴史家と接触している。勝三が昭和53年(1978)発行の本誌に寄せている自伝小説によると、勝三は戦後間もない昭和20年代、当時の横山八幡宮山根正三宮司の代に社務所に歴史編纂室を設けそこで古文書の解析と研究に没頭した。編纂室には連日の郷土歴史愛好家が訪れ、市内の旧家からでてきたという膨大な文書が集められたという。そんななかで昭和9年(1934)発刊の『宮古港大観と郷土の名所旧跡』(宮古日日新聞社刊)において「黒森神社御陵説」を唱えていた郷土史家・伊香弥七が自らが研究のために集めた資料を携えて現れる。伊香の持ってきた文書は多岐にわたったがそのなかに高橋子績の『南部封域志』『源廷尉義経』『黒森山稜誌』等があり、この文書の解析にあたった勝三は義経不死説のきっかけを掴むことになる。 勝三の小説によると、当初、横山八幡宮の歴史掘り起こしに没頭していた勝三は、伊香が持参した義経に関係する文書には惹かれなかったが、横山八幡宮の歴史が書かれた文書のなかにも義経や弁慶が登場することから、義経は平泉で討たれず、落ちのびこの地を通り北行したのではないかと考えるようになる。ちなみに勝三が影響された文書は『南部封域志』『横山八幡宮縁記』等でありどちらも江戸時代の漢学者・高橋子績の著書であっただ。奇しくも江戸時代の宮古にいた高橋子績と昭和の宮古にいた佐々木勝三は時代を超えて接触したのであった。 勝三はその後『横山八幡宮記』編纂と同時進行で、宮古下閉伊をはじめ上閉伊など県内の義経伝説が残る遺跡を訪ねてはそれらを丹念に取材するとともに、古老が語る地元の口伝を汲み上げ、独自の理論と推測で現在の義経北行伝説を組み立てた。のちそれら伝説の足跡は県観光連盟により「義経北行伝説コース」として紹介され私たちの知る義経ブームを巻き起こすことになるのだった。
義経伝説の誕生
源義経が平泉で討たれず何処かへ落ちのびたのではないか?という疑惑は当初から存在したと考えられるが、これがひとつの文書としてまとめられたのは、義経の死後約300年経った江戸初期の寛文10年(1670)に『続本朝通鑑(ぞくほんちょうつかん)』の47巻にはじまるという。本格的に義経が蝦夷を目指していたという説が唱えられたのは、江戸中期の元禄元年(1688)水戸藩の御用船が蝦夷地を探険しそれを紹介した年以降になる。この頃、江戸の劇作家・近松門左右衛門が『源義経将棊経(みなもとのよしつねしょうぎきょう)』を執筆、学者・新井白石が『蝦夷史』のなかで義経北行伝説について触れ、この時代の知識層がこれに触発され18世紀初期に義経北行伝説は巷に広がった。この風潮に乗り遅れまいと、様々な伝説を手本に多くの義経に関する創作が生まれた。同時にこの時代から、古記録を書き置く古文書ブームが巻き起こり、伝説主体型の文書が多数執筆されたという。この地における義経伝説に関係する文書を残した高橋子蹟もこの時代の人であり、古記録を後世に残すという大義名分のもと、各地に散らばる口伝を主体に義経が登場する神社縁起を多数執筆したと思われる。
義経と黒森山。義経伝説は江戸時代のエンターティーメントだった
黒森山はこの地方で古い時代から崇められてきた霊山であり、その名も九郎=黒森は響きも似ていればこそ、この黒森に立ち寄り祈願するのは自然の成り行きであろう。このような憶測が伝説となりやがて一人歩きしたのが義経北行伝説だ。それは江戸時代の文化であり娯楽でもあったようだ。明治・大正時代にはそれらを拾い集め多くの学者が義経の謎に迫った時期もあった。戦後、これが観光資源になると考え県観光協会では各地に義経北行伝説の看板を立てた。看板は黒森神社にもあり義経らが三年三ヶ月間黒森山に籠もり大般若経を写経したと伝えている。こうして伝説はその時代に合った新たな伝説を含み何十年かに一度掘り起こされては、誰かが足跡を辿る…。これが義経伝説の娯楽性であり義経の呪縛なのである。