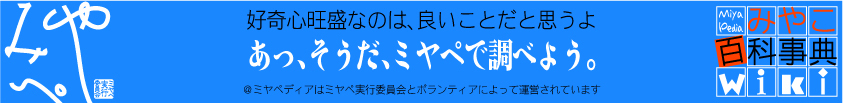筆満可勢
江戸末期の鍬ヶ崎が見えてくる旅芸人の道中日記
※道中日記『筆満可勢』は江戸の浄瑠璃芸人・富本繁太夫が文政11年から天保7年までの東北巡業を書き留めたもの。町の様子や興業の状況、まぐわった遊女のことなどを記した雑記帳だが支出入などが細かく記載され当時の経済状況や道路状況が見えてくる。原本は東北大学附属図書館にある。
筆満可勢の中に出てくる鍬ヶ崎
江戸時代、南部藩の軍港及び御用港として栄え、明治には三陸沿岸と塩釜を結ぶ三陸定期汽船の寄港地として古くから人と経済と文化の中心であった鍬ヶ崎は、古くから花街としての側面を持っていた。
鍬ヶ崎においての遊郭の歴史は、江戸中期頃会津の商人が現在の日影町付近に廓をひらいたという記録が日影町金勢神社の由来記にあるが定かではない。実際に鍬ヶ崎が遊郭として記録に出てくるのは江戸末の文化・文政期(1804~1829)で、この当時にはすでに盛岡の志家町の遊郭に鍬ヶ崎の遊女や芸妓が出稼ぎに出ていた記録もある。
文政11年(1828)から天保7年(1836)まで東北地方を中心に流浪した旅稼ぎの江戸の浄瑠璃芸人・富本繁太夫という人が残した『筆満可勢(ふでまかせ)』という道中日記に、花街鍬ヶ崎のことが記されていることから、この時代すでに鍬ヶ崎は花街として確立していたようだ。
当時の鍬ヶ崎は上町の山手に廓が軒をならべ向かいは砂浜であり「町屋三百許のうち、遊女六百十許」と記された記録もある。当時、全国的に遊女と芸者は同一視されていたが「鍬ヶ崎では器量よりも芸達者な女ほどよい女郎」という風潮があり、女郎・芸者とも皆芸事には熱心だったらしい。繁太夫たちは鍬ヶ崎でのお座敷興業と、芸妓に浄瑠璃の稽古をつけてくれるよう頼まれ鍬ヶ崎に入ったものらしい。
文政11年4月、山田より徒歩で宮古に入った繁太夫一行はとりあえず、宮古町の橘屋保兵衛方に宿を定め、興業や遊郭を仕切っていた目明かしや、箱番などに挨拶回りをして座敷や稽古をこなしていたが、宮古から毎日鍬ヶ崎へ通うのは難儀であり、のちに鍬ヶ崎の秋田屋に宿を移した。日記を見るとお座敷には宮古に入る前興業した山田の贔屓の旦那衆が舟で鍬ヶ崎に遊興に訪れることもしばしばあったらしく、人気も上々でそれなりに繁昌したらしい。ところで繁太夫、同行している相方であり弟子の三味線弾きの弥惣次は「横根」を患っており、宮古で医者にかかった記録がある。横根とは今で言う淋病、または梅毒のことで女郎買いが男の日常であった時代、性病を患ってもいささか不思議ではない。寛政12年(1800)に刊行された江戸風俗の記録によれば「この病、近世もっとも盛んにして、これに患ったもの男女十にその半ばに達する」とある。10人のうち5割が性病にかかっていたというのは極端だが、性病はそれだけポピュラーな病気だったらしい。
繁太夫と弥惣次は宮古の医師藤島柳的(りゅうてき)の元へ入院している。柳的という人は元々仙台で髪結いをしていた人で、どこで医術を学んだかはわからないが、「白膏薬(しろこうやく)」という薬を処方され、二人の病気は快方へ向かう。この薬は俗に「追出し薬」とされ現在の塩化第一水銀である。水銀療法は安永4年(1775)に来日したツンベルクという外国人医師によって紹介され、梅毒の切り札とした珍重された。しかし水銀による治療は初期梅毒には有効だが中毒と副作用があり危険な療法だ。 鍬ヶ崎に3ヶ月ほど逗留していた繁太夫一行だが、当時はよそ者の長逗留は御法度であったため、6月末、出立の時期となった。丁度、文政12年6月27日、紀伊様ご隠居(徳川重諭)が死去したことにより、全国に七日間の「鳴物御停止」のお触れがあり出立の気持ちも固まった。しかし、繁太夫らは、芸妓、遊女らに名残惜しいと乞われ「菱屋(現菱屋酒造の前身)」の土蔵で密かに浄瑠璃を演じている。また、盛岡城下への土産として鮑の塩漬けを拵え、贔屓客の徳島屋定八からは煎海鼠(いりこ)を餞別として受け取っている。宮古の煎海鼠は吉浜の干鮑、大船渡の鱶鰭とセットで、三陸名産の長崎俵物であり庶民には売買できないご禁制の品であった。
現在の閉街道(国道106号)を三日三晩をかけ歩いて盛岡へ向かった繁太夫は、その情景を次のように日記に記している「川の流れつよく岩石厳しく草木茂り景色ことのほかよろし」しかし、途中宿らしい宿はなく食べ物にも不自由した繁太夫は「甚だ難渋至極也」と結んでいる。繁太夫はその後盛岡で正月を迎え、春に秋田へ向かい、庄内へ入る。その後越後方面をさまよい、最終的には8年後京都で江戸の芸者と所帯をもつ。晩年は思うように声が出なくなり浄瑠璃太夫ではなく男芸者として太鼓持ちをして暮らしたが、日記『筆満可勢』以外の詳細等は不明だ。