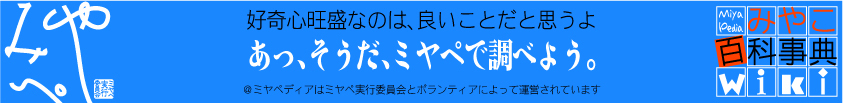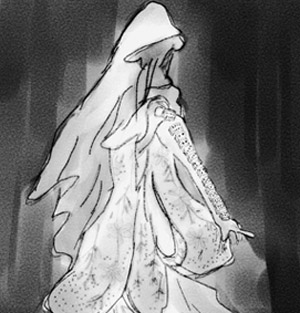カテゴリ:現代妖怪散歩
はじめに
ここに掲載している妖怪は月刊タウン誌・みやこわが町に2011年3月まで連載していたものをランダムに掲載したものです。これら妖怪は宮古とは 深く関係しているわけではありませんが、人の心にある嫉妬や憎悪、信仰や崇拝の中に存在する無形の畏怖でもあります。そんな妖怪をオリジナルイラストで現代風解釈でわかりやすく説明しています。
垢なめ
不潔な風呂や人が住んでいない廃墟におり、風呂のガビや汚れを食べるという
子供の頃、私の家には風呂がありませんでした。風呂がないわけですから銭湯へ行ったり風呂がある近所の家へおじゃまして、貰い風呂をする毎日でした。そんな貰い風呂をした家のうち、ある酒屋さんの外風呂が今でも記憶に残っています。その家の風呂は母屋から離れた場所にありまして、浴室に電気がありませんでした。ですからロウソクや小さな石油ランプを持って風呂に入ります。湯船は昔の棺桶にも似た木製で、お湯に入りながら釜に薪が投入できる、いわゆる「鉄砲釜」という形でした。そんな真っ暗な風呂に入るのは子供の私にとって耐え難い恐怖で、一緒に入ってくれる近所のおばさんやお姉さんの乳房にしがみついて恐ろしさに耐えたものです。
さて、風呂というものは年中湿気ており、昔はナメクジや「フルダ」と呼ばれる大ガマなどが棲息する場所でした。人は入浴して清潔になるというのに風呂そのものは木が腐れ、多くの人の垢や髪の毛が溜まり誠に不清潔なのです。そのような場所に好んで出るとされる妖怪が「垢なめ」です。
江戸時代の妖怪絵師・鳥山石燕は『画図百鬼夜行』において「垢ねぶり」として風呂小屋の入り口付近から半身、身を覗かせる子供のような姿で描いております。現代の妖怪絵師・水木しげるは『続・妖怪辞典』において、同様の子供らしい姿にざんばら髪で風呂桶そのものを舐める姿で描いています。「垢なめ」の特徴は異常に長い舌と、一本鈎爪の足です。この長い舌で湯船の内側に溜まった垢を舐め、鈎爪で木と木の間、いわゆる目地に溜まった垢やカビを掻き出して食べるのでしょうか。
江戸時代の随筆『百物語評判記・巻二』によると、「垢ねぶりというものは、古い風呂屋、荒屋敷に住むという。物は魚が水から生まれて水を呑むように、生まれたところの物を食うものであって、垢ねぶりも塵や垢の気が積もり積もって化生したのだ」とあります。この報告によれば、妖怪・垢なめは垢の上にまた垢が堆積し、ひとつの物体を作り上げたということになります。さすれば、垢なめの身体は垢そのもので出来ているわけで、垢なめは垢を食べてどんどん巨大化するわけです。
テレビアニメ「ゲゲゲの鬼太郎」では、垢なめは気の弱いおとなしい妖怪として描かれ、垢(赤)にちなんで真っ赤な身体で表現されました。物語の中で垢なめは浴室を舐めてピカピカにしてしまいます。垢なめは汚れた風呂場を隅々まで舐めてキレイにしてくれるので人間にとってはこのうえなく便利のように見えますが、それは垢なめが自分の存在を知らしめるためにやる行為であり、キレイになるのではなく半ば嫌がらせです。ペットが食事を終えて食器がピカピカになっていても、その器で人はご飯を食べられません。また、垢がたまってヌルヌルした風呂は不潔で誰でも嫌いなわけですが、垢で滑る(すべる・なめる)危険も考えられます。そんなことを考えると、妖怪垢なめは生活教訓をベースに生まれた妖怪であると見るべきでしょう。ただ、妖怪・垢なめは基本的に垢の塊ですから、タンパク質が腐敗したかなりの異臭が漂う妖怪のはずなのですが、残念ながらその臭いについての記述は見あたりません。
白粉婆
夜の雪原をとっくりを持って徘徊する雪女の変形版。遣り手婆のなれの果てか
妖怪の分類も色々とあって、人型、動物型、物器型、鬼型、火炎型などがありまして、これらをまた細かく分けると、動物型なら狐、猿、狸、鳥、蛇、魚などとカテゴライズされます。ちなみに人型は、女、男、童子、老人に分けられまして、女は○○女、童子は○○小僧などと呼ばれ、老人は○○婆、○○爺と呼ばれます。婆の代表は『ゲゲゲの鬼太郎』でおなじみの「砂かけ婆」でしょうか。となれば爺の代表は「子泣き爺」となりますかね。
さて、とかく人間も物器も長年の歳を経てまいりますと、物の怪となりまして通常の思考能力では理解できない現象を引き起こすものです。特に平均寿命が延びて超高齢化社会となった現代におきまして、爺・婆のひきおこす怪異は身近になりました。そんな中、今回は婆系妖怪の中から「白粉婆」を紹介します。
白粉婆は寒い雪の日の夜、大きな傘をかぶり、酒のとっくりを手に酒を求めてうろつき歩く老婆の妖怪です。単に酒を買いに徘徊するだけの妖怪ですから迷惑をかけないのですが、妖怪の本質というか、妖怪たる所以として間接的に人に迷惑をかける素質をもっています。白粉婆の場合年老いた醜い顔にたっぷりと塗り込まれた白粉です。辺り一面雪が積もって真っ白になった雪の夜は月明かりぐらいでも充分に目視で相手の顔が確認できます。もし、とっくりをぶら下げて向こうから歩いてくるおばあさんが大きな傘の下から真っ白い顔を出したらだれでも腰を抜かしてしまいます。
岩泉町の有名な老舗お菓子屋さんに「たんもうれ」という銘菓があって、これはマッチがなかった昔、種火をもらい歩いた古事によるものだと説明されています。しかしこれも老婆が釣り鐘状の火壺をぶら下げて「ひっこー、たんもーれ(種火をください)」と口にしながら夕闇を徘徊したら、それが通常のおばあさんでも遠目には妖怪に見えてしまいます。
江戸時代の妖怪絵師・鳥山石燕は『今昔百鬼拾遺』においてとっくりを持って雪野原を歩く白粉婆を描き「紅白粉の神を脂粉仙娘(じふんせんじょう)と云う。おしろい婆は此の神の侍女なるべし」と語り「恐ろしきもの、師走の月夜、女の気配と昔よりいいけり」と添え書きしています。このコメントは12月は身支度も暇がないぐらい忙しいのに、入念に化粧をした女の気配はそら恐ろしいという意味らしです。
藤沢衛彦(ふじさわもりひこ)の『日本民俗学全集3』では能登地方で大きな傘をかぶって雪の夜に酒を買いに行く老婆を言う、と説明しており、この説が現代の妖怪絵師・水木しげる氏の『妖怪辞典』などの妖怪連作の中にも見えます。しかし、実際に能登地方には白粉婆のような伝承はなく、これは藤沢氏の創作ではなかったかとされています。
そんな背景から白粉婆とは遊郭などで女郎とお客の世話を取り持つ「遣り手婆」のなれの果てではないかと思います。廻し部屋の階段下に帳場机を置いて手あぶりにのせた鉄瓶でお燗をつける…。そんな揚屋(あげや)のフロアマネージャー・遣り手婆も以前はその郭(くるわ)のお女郎だったわけで、なんだか悲しい運命を感じます。
にわとりの僧
僧の戒律を破って盗んだニワトリを食った僧の身体に現れた怪異とは
今回は昔話からお話を進めたいと思います。
江戸時代のお話です。ある山奥のお寺に修行中の若い坊さんがおりました。朝は暗いうちから起きて読経し、午前中は写経と座禅、午後は里に下りて托鉢の毎日でした。寺での食事は僅かばかりの粥と漬け物程度なので育ち盛りの若い僧は空腹から食べ物を腹一杯食べる夢に魘(うな)されては己の未熟な心に浮かび上がる幻影を恨み一心に経を読んでは仏の道を追求するのでした。
そんなある時、村の庄屋の若旦那が亡くなりました。若い僧も住職に伴って菩提を弔うため何度も庄屋の家に招かれお経を唱えました。盛大なお通夜も終わり棺桶に入った若旦那の遺体がお寺に運ばれてきました。若い僧は住職の言いつけで、若旦那の遺体の髪を剃髪することになりました。昔からこの寺では釈迦の血脈をもらい宗教者としてあの世へ旅立つため、遺体の髪を剃り僧形にしなければなりませんでした。若い僧も遺体の剃髪ははじめてではないので手慣れた手つきで桶の蓋を開けると若旦那の髪を剃髪しました。その時です、誤って剃刀が頭部の皮膚を削いでしまったのでした。それは冷たい肉片でした。若い僧の心には二つの気持ちが同時に浮かびました。それは、大変な事をしてしまった…という気持ちと、その肉片を食べたいという欲望でした。
それからこの寺ではしばしば墓が暴かれる事件が発生しましたが、数年後、若い修行僧が寺を出て行ってから不思議と事件はピタリと治まり、墓が暴かれることはなっかたそうです。
昔は墓が暴かれるということは結構あったようです。動物が掘り起こして遺体を食い荒らすのはもとより、罰当たりな輩が三途の川の渡り銭として死人に持たせた六文銭や死人と一緒に棺桶に入れた故人の貴重品目当てで荒らしたのでしょうか。また、江戸時代には人の頭骨(ドクロ)を御神体として崇める真言立川流などの怪しい宗教もあったようで、土葬方式だと埋葬してからも安心できなかったようです。そのため魔除けとして墓に鎌を挿したりする土葬墓地独特の呪(まじない)は多岐にわたって様々なものがあるようです。
僧侶に対する戒めは多々あり、特に生臭物とされる肉や魚を食べないという戒律があります。現代においてはイタメシ屋とか寿司屋で食事する坊さんもいますから戒めは都合よく解釈されているのでしょう。さて、昔、ある僧が寺の隣の農家で飼っていた鶏(ニワトリ)を盗んで焼いて食いました。しかし、これを見ていた人が住職に報告、鶏を盗んだ僧は住職に詰問されました。最初は知らぬ存ぜぬを通していたのですがやがて僧の口と尻から鶏が現れ鶏を食べたことが発覚したそうです。
現代の妖怪絵師・水木しげるは子供向けの著書『妖怪100物語』でこれを取り上げ「にわとりの僧」として口から鶏の頭が出ている不気味な僧を描いています。私のイラストもこの流れを汲んでいますがモデルはトリインフルエンザ等の伝染病で大量の鶏を生きたまま処分してしまう経営者を恨む鶏の妖怪というイメージです。
山精(さんせい)
山精は鉄山で廃人になるまで働かされた労働者のなれの果てではないのか
盛岡名物と言えばじゃじゃ麺や冷麺わんこそば、そして南部鉄器も有名です。南部鉄器の工房は盛岡城があった盛岡周辺に多いわけですが、周辺に鉄の鉱脈があるとか、砂鉄が取れる河川があるわけではありません。南部鉄器の鉄は下閉伊郡内に無数に点在していた鉄山(てつざん)と呼ばれる小規模な精錬所で延鉄として生産され、南部牛の背中に揺られながら城下に運ばれたものなのです。鉄山で働いていたのはヤマセによる冷害の影響を受けやすい沿岸部の農家から払えない年貢の代償として男たちがかり出され過酷な労働を余儀なくされていたようです。当時、鉄山で働くことを「鉄山かせぎ」と呼びましたが一年で髪の毛が白くなり、二年で髪の毛が抜け落ちるという人知を超えた過重労働で多くの人が命を落としました。鉄山を牛耳っていた役人たちは逃げ出す者をあらゆる手段で捕縛し牢につなぎ見せしめとしました。藩直営という名目でしたが経営はずさんで人夫の給金をピンハネし役人たちはおおいに私腹を肥やしました。これに対し沿岸の農民漁民たちは日本最大規模とも言える嘉永・弘化の一揆で鉄山経営者らの蔵や私邸を打ち壊しています。
鉄は人の工夫によって釘などの建築物、鍬や鋤などの農機具、そして刀や槍などの武器にまで応用可能な金属です。極端な話、金を得るなら途方もない時間をかけて砂金を集めるより、誰かが集めた砂金を鉄の武力で奪う方が楽なわけです。義経をめぐる源頼朝の野望も奥州の金はもとよより、武器を製造する鉄にあったと考えてもあながち的は外れていないと思われます。
当時の初歩的鉄精錬は炉の中に砂鉄と炭を混ぜて薪で加熱し鉄を溶かし型に流すもので、高温を保つため大型の鞴(ふいご)で空気を送り込みました。現場は輻射熱によりもの凄い暑さで作業に当たる男たちは大量に汗をかくので塩を舐めながらひたすら鞴を踏みました。また溶けた鉄の熱と光により視力も衰えました。過労と栄養失調で毎日鞴を踏むため脚の関節は砕け不虞者となり戦力外とされ野山をさまよう者もいました。そんな人が獣を捕るため猟師がかけたマタギ小屋に入り込み塩を盗んだりしました。これが山精と呼ばれる妖怪の正体です。江戸の妖怪絵師・鳥山石燕は『今昔画図・続百鬼』で中国の山鬼として紹介し、人のようだが一足で木こりの小屋から塩を盗み石蟹(サワガニ)を炙り食らう。と説明しています。現代の妖怪絵師・水木しげる氏も同様の絵で山精を説明し、山精は何も悪いことはしないただ塩がすきなだけなのだ…と記しています。ただ、石燕の絵は明らかに一足で脚の方向が不自然に描かれ、手には蟹を持っていますが、水木氏はこれを蟹ではなくもう片方の足首を持つ姿に書き替えています。これは水木氏が鉄精錬に伴う脚の不虞、塩の摂取までを読み切らず石燕の絵を現代風に置き換えてしまったのかも知れません。当の石燕も江戸後期の百科事典でもある『和漢三才図絵』を参照しているだけなので、山精と製鉄を結びつけて考えていないという見方もあります。私のイラストは精錬で焼けた肌に一足の山精が昭和40年代の塩販売許可のある雑貨屋を電柱の影から覗く姿としました。
砂かけ婆
砂かけ婆の本当の意味を考える
砂かけ婆といえばテレビアニメ・ゲゲゲの鬼太郎(以下鬼太郎)において、鬼太郎ファミリーの中核的存在で描かれ鬼太郎と目玉のオヤジのよき理解者でもある老婆の姿をした妖怪です。実写映画ゲゲゲの鬼太郎では、女優・室井滋が砂かけ婆役を好演しており、いつしか間寛平演じる子泣き爺と内縁関係の老カップルのように設定され人間の味方的含みをもった善玉妖怪として定着しています。鬼太郎の原作者・水木しげる氏は数ある著書の中で砂かけ婆について触れ、奈良県のとある竹藪の中に住んでいる妖怪で、時々神社などの竹藪に出没しては砂をパラパラと撒いて人を驚かす。砂の音に驚いて辺りを見回しても誰もいないわけで、そんなたわいもないいたずらをしては楽しんでいる…。と説明しています。このような誰もいない所から砂が飛んでくる怪現象については、民俗学の先駆者であり遠野物語で有名な柳田国男も柳田国男全集『妖怪談義』の中で全国の事例を集め、その現象が鳥や動物が身体の表面に付いたダニや寄生虫を落とすためにやる「砂浴び」ではないのか?と推測しています。これはタヌキなどが砂浴びをして身体に砂をまとったまま木に登り高所において砂を振り払い、その砂粒が通行人に降り注いだものではないか?と説明し、なんとそのような現象を柳田自らも若い頃に武蔵野で経験したことがあったと記述しています。
さて、妖怪というカテゴリで呼ばれる様々なものは歳を経た物器から狐狸、珍しい自然現象、特異な世界で暮らす隔離された人たちをさすわけですが、これらは往々にして人に対して迷惑をかけることでその存在を知らしめています。はっきり言って人にとって都合のいい事をする妖怪は100%存在せず、大なり小なりひたすら迷惑をかけます。砂かけ婆もその例外ではなく人に迷惑をかけるわけで、水木氏が言うように人知れず砂を撒いては姿を隠しほくそ笑んでいるかも知れませんし、柳田氏の言うように狐狸の類が高い木の上から砂を撒くのかも知れません。しかし、私は砂かけ婆が人に対して行う迷惑の正体がそんな可愛いものではないと思います。そしてその迷惑こそを探れば古来から語られてきた砂かけ婆の真の姿が明解されるのではないかと思います。
砂かけ、という現象を目に砂が入ったりすると考えてしまうと自然と水木・柳田論へと導かれます。しかし、砂かけ、が摩擦や軋轢を増長させる行為や言葉と考えればどうでしょう?砂かけ現象とは、円滑な状態に摩擦を加えギスギスした関係へと導くことではないでしょうか?では、砂かけ現象に悩まされるシーンとはどんな時でしょう?それは夜に息子夫婦の寝所に向かって母親が声を掛けたりして、その大切な夫婦の営みを邪魔するような行為ではないでしょうか。母親がささいなことで何度も何度も息子を呼びつけ、夫婦の長い夜にまさしく、砂を撒いて邪魔をするわけです。
砂かけ婆とは、竹藪ではなく普通に家にいて、砂ではなく、グチや嫌がらせを撒き散らし、息子夫婦の関係に軋轢を生じさせ、しいてはその家の団らんすらギスギスした関係へと導く、母親の心に燻る我が子可愛さの歪なわがままが妖怪化したものだったのではないでしょうか。
二口女
女の怖さを知らしめる貧乏神の変形版か
私が少年時代だった昭和40年代はマンガ本は各自が買うのではなく貸本屋で借りるのが普通でした。貸本屋は少年たちのたまり場で少年マガジン、サンデーのような週刊マンガはもちろん、ぼくら、冒険王、少年画報などの月刊誌も貸していましたし、月刊誌に付録でついてくる読み切りの冊子にも個別に表紙を付けて貸していました。それらは町内のガキ大将グループが優先的に最新号を借りるため、年下の少年たちはおこぼれのような古いマンガしか借りられませんでしたから、普通の少年たちはいつもマンガに飢えていました。今回はそんな時代の話からしましょう。
恐がりなくせにお化けや妖怪が好きだった私は、夏休みに当時釜石に住んでいた従兄弟の家に泊まりに行きました。そこには私より1つ下の男の子と2つ年上のお姉さんがいて、姉弟の勉強部屋の本棚には図鑑や辞典に混じってマンガ本がずらりと並んでいました。マンガは貸本でしか読めない私にとって夢のような光景ですから、泊まりに行くと朝から暗くなるまでマンガ三昧でした。
そんなマンガの中にお姉さんの女の子系月刊マンガの付録と思われる短編読みきりの恐怖マンガがありました。題は『呪いのこぶがチチチとまた呼ぶ』です。サイズはA5版で印刷はザラ紙にマゼンダ(紅色)で印刷されていました。作者は覚えていないのですがきっと『エコエコアザラク黒井ミサ』の古賀新一だと思います。あの頃少女マンガの恐怖路線は『へび少女』の梅図かずをと古賀新一の両巨塔が支配していたましたし、梅図氏の絵とは違うタッチでしたから古賀新一だと推測するわけです。物語は少女の手の甲にできたオデキがやがて人の顔のような人面痩となりオデキの口から虫やトカゲを食べるようになります。少女は意を決しこれを自ら焼いたナイフで切り取ってしまうのですが後日人面痩はまた現れじきに少女の全身に広がってゆくのでした。私はこれを読んで生まれてはじめて本当に恐怖を感じ、このマンガが今でも私のトラウマになっています。
さて人面痩とは奇病の一種で医学的報告でも実際にあったらしいのですが、オデキの顔が虫やトカゲを食べたり飯や酒を飲む、それこそ「チチチ」と鳴いたりするのは創作でしょう。しかし、オデキが人の顔、しかも見覚えのある人の顔に見えたら精神的にかなり追い込まれるのは当然でありその恨み効果はさぞ抜群でしょう。しかし、後天的に人の身体に顔が現れるという怖さより最初から別の顔があるという怖さもあります。夜叉や明王などは三面六臂などのように顔や腕が幾つもあっても怖いというより威厳や厳格さを感じますが、後頭部に大きな口があってそこから多量の飯を食うという二口女はどうでしょう?金持ちのくせにケチな男の元に嫁いだ女は飯も食わずに働きますが、夫がいなくなると後頭部の口から何でも食べてしまいます。これは宮古下閉伊にも伝わる『口のない嫁』という二口女の話です。
見た目はきれいで働き者、しかしその実態はもうひとつの口から大量に消費してその家を衰退させるのが二口女の実態です。ある種の貧乏神であり、女の怖さを知らしめる教訓でもあります。うわべでは優しい話をしますが影では悪口三昧、そして土地財産から権力まで二つ目の口でぺろりと食ってしまいます。
百々目鬼(どどめき)
見られたかも…という猜疑心が生んだ妖怪百々目鬼
人の感覚器官の中でもかなり重要なウェイトを占めているのが目です。極端な話、人は朝目を開けることから活動を開始して夜目を閉じることで活動を終えスリープ状態となりますから人の活動の約90%以上が目に影響していると言っても過言ではないでしょう。
何でも見える、見てしまう私たちの目ですが、ごく希にその人だけにしか見えないイレギュラーを発します。これは目が脳以外の自律神経の影響も受けるためで目に限ったことではなく耳や鼻、手や足、皮膚などにも当てはまります。耳ならふとした時に自分だけが聞こえる幻聴がありますし「空耳」もあります。これと同じことが目にもあって精神的な影響や自己暗示、思い込みや第三者による脅迫などでその人にしか見えない「幻」が発生します。それが見える人にとってごく普通に感覚器官が捉えているため幻であることが判らないし、それが見えない人にとって見える人の話が理解できません。こんなすれ違いが心霊現象やUFOなどの目撃談の真相ではないでしょうか。だから人は証拠が欲しいためおばけの写真やUFOのVTR分析にこだわるのだと思います。これらは気まぐれな人の目が作る画像的錯覚論争のイタチごっこなのかも知れません。
目は見るための器官であるがために人は見られるという状態を意識します。奇抜なファッションで人目を引きたいと思う人もいる反面、できるだけ人混みの中に紛れて自分の存在を希薄にしたい人もいます。複数の中に紛れ保護色をまとう者は少なからず隠者や犯罪者的心理と「だれも見てないからいいや…」という自己中心的甘えがあります。そして同時に「だれかに見られたらどうしよう」という不安が首をもたげます。何億分の1の確立ですが都会の雑踏のなかで百年の仇にばったり出会ったり、マイナーな山峡の温泉で逢瀬を続ける不倫のカップルがいつか知り合いに会ってしまう可能性だってあるわけです。そんな疑心暗鬼がどんな立派な人でも心のどこかに燻っているものです。そんなわけで見る、見られる、見せるなどの行為において重要な「目」にかかわる妖怪は古くから多数存在するようです。
ある女スリがいつもの仕事を終えて古い御宮の裏手に回り獲物の財布から金を抜いているとどこからか視線を感じ、慌てて財布を懐にしまったのですが周りにはだれもいません。しかし見られている気配は感じるわけです。おかしいなと首を傾げた女スリは自慢の左腕の着物の袖をまくり上げたところ腕には無数の目があり自分を見ていたそうです。これが妖怪・百々目鬼で人の心の奥底にある猜疑心から生まれた妖怪です。また、見られている気配を感じてしまうのは、後ろめたさからくる不安もあります。誰もいないはずの廃屋で、なにやら怪しい行為に及んでいると障子にみるみる目が発生して数百の視線を感じる錯覚に陥るといいます。これが妖怪・目々連で、まさに諺の「壁に耳あり、障子に目あり」です。
今回の妖怪イラストは前述の女スリの腕に現れた妖怪・百々目鬼ですが、なんとそれは麻雀の筒子(ぴんず)限定の役満「現代車輪」という設定。この手は二筒から八筒まで二枚づつ集めて完成するめったにお目にかからない役満です。
ひょうすべ
ひょうすべと河童の意外な共通点とは
江戸の妖怪絵師・鳥山石燕の『画図百鬼夜行・前編・風』に頭がつるっぱげで全身がけむくじゃらで両手を肘から上げた状態の、ひやうすべ(以後ひょうすべ)が描かれています。絵にはおそらく厠などの離れに連結するであろう直角に曲がった廊下と、ひょうすべの手前には手洗い用の水差し、ナンテン(南天・植物)、廊下を曲がった奥には火がともった灯明皿が描き込まれています。絵の右上には充分な空白がありそこに「ひやうすべ」とあり全く説明がありません。ちなみにどうしてナンテンと手水差しだと判るかと言いますと、ポットのような格好の水差しは深いお盆に置かれ湯飲みがありませんから水差しが飲料用ではないことを表します。おそらく客人が用を足した手を水差しの水で軽く洗い汚水はお盆に溜め、女中がそれを捨てたのでしょう。ナンテンは祝いの赤飯の掛け紙のイラストと同じだからです。ナンテンは「難転」とシャレて「災い転じて福となる」の縁起も担ぐわけで、庭に植えておくといつかいいことがあるという、日本版の幸福の木ですから目出度い席の引き出物の図柄に持ってこいです。厠のそばにナンテンがあるのは暗い厠で転んだりした時、ナンテンを触って「災い転じて…」のジンクスにあやかろうという縁起担ぎからです。
便所の帰りに転んだりすることは今も昔も相当に縁起が悪い予兆で、数日後に死ぬとさえ言われます。酒を飲んだりして足元がおぼつかないのに離れにある厠まで行って用を足すのは危険でしたし、昔は屋根がついた縁側とは言え起きている時は雨戸を開けていますから廊下は外の気温と同じです。さぞかし厠への往復で脳梗塞や脳卒中になることも多かったでしょうし、テレビ時代劇の必殺シリーズでも厠に関係した必殺シーンはよくあるパターンです。というより昔は今よりぐんと厠で人が死ぬことが多かったのを物語っているのではないでしょうか。
ではどうして石燕はひょうすべが厠を連想する場所にいる絵を描いたのでしょう?これには色々な説があるのですが、私は厠が「川屋」、すなわち元祖ジャパニーズ水洗トイレに連動しているからだと思います。柳田国男と双璧をなす民俗学の先駆者・折口信夫によりますと、ひょうすべは大和国の兵主神(ひょうずのかみ)の末でかつては北は奥州から南は九州まで信仰を集めたが、これがのちに廃れたものではないか?としています。しかも、兵主神を祀る奈良県桜井市の穴師坐(あなしにいます)兵主神社にはなんと相撲発祥の相撲神社も祀られています。ここまでくれば賢明な妖怪好きなら「ははーん」とひらめきます。ひょうすべは河童と密接な関係があります、というより河童の亜種と考えるべきでしょうか。柳田は水に関するライフラインの整備により元来崇められていた水神が零落し河童となったと論じていますし、俗に相撲好きで頭頂部がツルツルなのもひょうすべと共通します。河童はその後も鴨、蛙、亀(すっぽん)などと合体しひょうすべとは別物の姿へと進化しますが、どちらも水神信仰をバックボーンに持っているようです。
宮古地方での河童の目撃談によりますと、赤い顔だったとの報告が多いようです。これはおそらくひょうすべであり、その正体は水で体毛がすっかり濡れた猿ではなかったのか?と私は推測しています。
おとろし
絵師の読み間違いが妖怪の正体を暴きにくくしたのかも
江戸の妖怪絵師・鳥山石燕の『画図百鬼夜行・前編・風』に長い前髪を垂らして神社の鳥居にかじりついている妖怪・おとろしが描かれています。絵は左下に重心を置いた独特の構図で鳥居の横木が約30度の角度で見える位置からの描画ですから、おとろしが鳥居にとり憑いている光景をさらに上から見下ろした図ということになります。おとろしは長い毛に覆われ、左の手と思われる三本のかぎ爪で鳥居を掴み、同時に太い牙で鳥居の横木にかじりついて、なぜか右手では鳥をわしづかみにしています。この絵から想像するとおとろしは巨大な顔だけの妖怪で湧き上がるような長い髪の毛と前に垂らした前髪が特徴のように見えます。現代の妖怪絵師・水木しげるは石燕の絵を参照にして毛むくじゃらで大きな顔だけの妖怪を竹藪と崩れた土塀をバックに描き、廃屋などで感じる怪しい気配の正体であり、うらぶれた神社にいる「つくも神」でもあると説明し、神社に不審者が近寄ると鳥居からどすんと落ちてきて脅かすのだと説明しています。
石燕は先達が描いた妖怪画や中国の俗画などを参考にしており、『嬉遊笑・覧』(喜多村いんてい・著)に挙げられている化け物の中から「おとろん」という妖怪を見つけこれを参照におとろしを描いたのではないかとされています。この時石燕が「ん」を「し」と読み間違えた、または関西・北陸で「恐ろしい」を「おとろし」と言うことから、おとろしとした可能性があります。表記が変体仮名であれば漢字と連動しているため読み間違いは少ないのですが、崩した草書のひらがなの「ん」が「し」に見えることはよくあることです。加えて石燕が参照にした『嬉遊笑・覧』を執筆した喜多村いんてい自身も、化け物画の先達、佐脇崇之(さわきすうし)の『百鬼図画』を参照しておりまして、そちらには同様の妖怪が「おどろおどろ」の名で登場しています。そして当時の記載の特徴として同音で発せられる言葉を表記する場合「おどろ(繰返略記号)」と書くわけで、この繰り返し記号が「ん」と誤読させれ、次いで「ん」が「し」と誤読され、そのまま現代に伝わり妖怪・おとろしが誕生したわけです。ちなみにおどろは「棘」と書きイバラなどの棘のある低木が乱れ茂っている様子や、クシも入れずに乱れた髪などを表す言葉で、これを重複させた「おどろおどろ」は目・耳を驚かせる怪異、気味が悪い、恐ろしいという意味で源氏物語や竹取物語でも使われる古語でもあります。
絵師たちの誤読によって名前が変化した妖怪・おとろしですがその姿は継承されているようでして、最大の特徴である垂れ下がった前髪は健在です。しかしこれが前髪ではなく寒さのために寄り集まった猿たちの尻尾とみればどうでしょうか?毛むくじゃらの猿が鳥居の上でダンゴになっていて、賽銭ドロの目の前に落ちてきたら後ろめたさもあってさぞ腰を抜かすことでしょう。
最後に石燕のおとろしが左手でわしづかみにしている鳥の謎解きです。神社には眷属という発想があって稲荷神社ならダキニ天と習合したお狐、日吉神社のお猿などが有名です。掴んでいる鳥が鳩なら、八幡神の眷属です。神社を守る妖怪が八幡神の眷属を掴み殺すのは納得できない図柄です。石燕はここになんらかの仕掛けをしたのだと思われますが謎のままです。現代におとろしを描き継いだ水木しげるは鳥居と捕まれた鳥を省いていますから、この謎を探っているのは妖怪オタクの好き者だけでしょう。
大禿(おおかぶろ)
廓という異空間に潜む男禿の怪しい色気とは
禿(かむろ、或いはかぶろ)とは遊郭の花魁の部屋で育ち、やがて身を売る定めをもった少女です。これに対して「男禿」とは遊女の産んだ引き取り手のない子や、貧しい家から廓や岡場所に売られてきた男の子たちで、遊郭の小間使いをする少年のことです。髪型は禿も男禿も同一のおかっぱで、廓では一定の年齢に達するまで男女の性の区別なく同一視されていました。禿は花魁道中で花魁の水先案内をする童子でもあり、これは現代の結婚式で花嫁行列の先頭に立つ男の子と女の子が扮する雄蝶、雌蝶と同等です。花魁道中は花魁を買い上げた客が待つ揚屋まで花魁が移動する行列で贔屓の禿、妹芸者(遊女)、世話をする髪結いや荷物持ち、下女、用心棒までを引き連れて、一夜ではありますが客の妻として嫁入りする重要な行為です。客は花魁を女として買うのではなく、花魁を神と見立て神と交わる行為により幸運にあやかろうという願いが込められています。現代の結婚式の花嫁行列の底辺にもそんな神世の風習が流れているのです。
さて、そんなことより禿の話でした。江戸も元禄を過ぎる頃、吉原などの岡場所遊びも多様化して、手続きが面倒で割高な吉原より手軽で格安な深川や本郷あたりの格下の遊郭や、半ば素人による茶屋売春などが流行るわけですが、裕福な豪商たちは花魁の御利益にあやかろうと吉原へ通いました。しかし、そのうち普通の廓遊びでは満足しなくなり、花魁とは別に女髪を結い女物の着物で着飾った男禿に触手を伸ばすことが一部で流行しました。男禿は一定の年齢に達すると遊郭では邪魔者でしたし、そんなニーズがあるなら男だろうと仕込んでしまうのが性の町・吉原です。男禿を女装させ床技も仕込む専門業者もおり、あくなき性への探求とそれを商売にする人の根性は今も昔も変わってはおりません。
江戸の妖怪絵師・鳥山石燕の『今昔画図続百鬼・巻之下明』に菊柄の着物に長髪で行灯を手に屏風の後ろに立つ大禿が描かれています。石燕は、中国の仙人・彭祖(ほうそ)は猶慈童(ゆうじどう)と称し七百歳まで生きた、是大禿にあらずや…。と解説し加えて、日本の那智高野には頭禿に歯豁(ひらく・あばら)なる大禿ありと云。と書き込んでいます。女人禁制の仏教方面にも昔から僧侶が弄ぶための稚児童子がいたとされ石燕は高野山にも大禿がいるのだと言っております。
妖怪大禿は老人に達しているのに少年の恰好をした男禿であり、同性愛者を表現しています。その着物には菊の花の露を飲んで不老長寿になった仙人・彭祖の別名「菊慈童」の逸話にあやかり、かつ、同性愛における肛門交合の象徴「菊」の柄がある着物を着ています。江戸時代の吉原では男禿の見世(お披露目)は菊にあやかり菊の節句九月九日の重陽の日だったと記録にあります。ちなみに現代の妖怪絵師・水木しげる氏は息を吹きかけられると怠け者になるという、女装した妖怪・いやみ(正式には否々(いやや))は現代に甦らせましたが、売春が生業の廓に出没する大禿は発生が子供向けではないためか彼の妖怪図鑑にはラインナップされなかったようです。
加牟波理入道(がんばりにゅうどう)
がんばり、にゅーっと、ほどほどに…?
近年はウォシュレットが普及し腰掛け式の洋式便器が主流で昔ながらの和式便器はぐんと減りました。聞けば自宅が洋式トイレなため学校の和式トイレで用をたせない子供も多くなり社会現象ともなっているらしいです。かく言う私の家もウォシュレット+洋式トイレですから外出時どうしても和式しかない場合を除きトイレは洋式派なわけです。
さて、トイレには昔から迷信や禁忌が多数あって、それに伴う怪異や怪談も多数語り継がれてきました。これはトイレが土中の穴に通じ穴は冥府や地獄へとつながっていると信じられてきたからです。だからトイレで転ぶと身内の寿命が縮む、トイレに落ちると出世しない、トイレで痰や唾を吐くと厠神に祟られるなどの禁忌が語られてきました。トイレに関する妖怪は小学生たちの間では都市伝説ともなっているトイレの花子さんが有名ですが、今やほとんどが水洗化している学校のトイレでは怪異はあっても妖怪は似合いません。やはり妖怪はトイレという英語の響きではなく便所、あるいは厠という和風な場所に出没するものです。 私が子供の頃、ある老人から聞いた話によりますと、汲み取り式の古い和式便所に溜まった排泄物の中から黒手(くろで)という真っ黒い手だけの妖怪が出てきて用を足す人のお尻を触るという話を聞きました。
江戸の妖怪絵師・鳥山石燕の『今昔画図百鬼・巻之中・晦』に便所の溜枡からわいてきて厠の中を外から覗く、加牟波理入道(がんばりにゅうどう)が描かれています。絵は離れの厠の裏に万年青(オモト・植物)と石柱に載った龍と獅子の手水瓶があり、加牟波理入道は厠の窓を覗きながら口から小鳥を吐き出しています。絵には説明があり「大晦日の夜、厠に行き、がんばり入道ほととぎす」と唱えれば妖怪を見ざるよし、俗世のしる所也…云々」とし、また、石燕は中国の厠神の名は郭登(くはくとう)といい、これは遊天飛騎大殺将軍として人に禍福を与えると説明しています。郭登は「かくとう」と読み明の時代の中国の武将らしいのですがそれがどうして厠神なのかは不明です。また、石燕はホトトギスに漢字で郭公の文字を当てているのも不思議です。実際にホトトギスはカッコウ目・カッコウ科の渡り鳥でカッコウと同様に他の野鳥の巣に托卵する習性がありますから学術的にも類似しています。ホトトギスの鳴き声は「キョッキョッ キョキョキョキョ」と聞こえこれを聞きなしで「テッペンカケタカ」とか「特許許可局」と言い表します。きっとこれが江戸時代の人たちには不吉な語句として聞こえたのでしょう。
ろくに野菜も食べず穀物主体の食生活の中で江戸の人々は極度の便秘だったと思われます。厠で窮屈にしゃがみながらお腹を押したりさすったりして固くなった便を肛門から出すのはそれこそいきんで頑張らなければなりません。加牟波理入道とは「がんばり、にゅーっと、ほどほどに…」案外こんな語呂合わせが生んだ妖怪かも知れません。

蛸神さま
野田・十府ヶ浦に祀られた綿津海神社のヌシは蛸だった?
宮古から国道45号線を久慈方面へ北上すると野田村があります。野田村は江戸の頃、塩炊きが盛んで製塩した塩をカマスに詰めて城下へ運んだという逸話があります。そんな野田村には陸中海岸では珍しい長い砂浜の海岸線があります。海岸線の南側と北側は消波ブロックで護岸されていますが、大きな弓状に開いた中央部は自然のままの砂浜になっています。この海岸は十府ヶ浦と呼ばれ風光明媚な景色が楽しめ、毎年7月の最終土日には野田砂まつりが開催され多くの人で賑わいます。
そんな十府ヶ浦海岸の南側に米田川という小さな川が流れ込んでおりまして、国道にもこの川を越えるため小さな橋が架かっています。もっとも、米田川の河口は十府ヶ浦の砂に隠され太平洋に注ぐ川の水は砂の下を流れているようですから、クルマを運転してこの川を通過しても川ではなく池や沼を通過したような感覚です。この川が盛り上がった砂によって埋没するあたりに風化した鳥居が建っておりまして申し訳ないぐらいの小さな社があります。この神社は海神(以後・綿津海・わだつみ)神社という名前で昭和8年の津波で流失、その後十府ヶ浦の防風林がある国道沿いに移転遷宮し見違えるような立派な神社になりました。今も砂浜に残る小祠は神様のぬけ殻なのですが漁師さんらが祀り現在に至るわけです。
さて、ここからが本題です。伝説によると海の神様でもある綿津海神社の脇を流れる米田川のヌシは蛸だと言うのです。一説によると綿津海神社の祭礼が近づくと何故か時化の日が続き砂浜に埋もれた米田川の淀みが緑色に変色するのだそうです。これを見た村人たちは「米田川の淀みヌシが入った」と神社に供物を捧げ崇め祀ったそうです。
野田十府ヶ浦がモデルのこの話は現代の妖怪絵師・水木しげるが自著『妖怪100物語』で紹介しておりまして、岩手県野田町米田という所に蛸神の祠があり祭りは毎年9月19日でこの時期が海が荒れて大沼が濁ると説明しています。また祭神になっている蛸神は昔、村の女が草刈りをしていて大蛸を発見し鎌でその足を一本切ってしまった際、にわかに空が曇り海が荒れ舟が流されてしまった、これが蛸神の祟りではないかと七本足になった蛸を祀ったところ嵐がおさまったのだそうです。そして、以後この地区の漁民たちは蛸を食べなくなった…。と、語っております。
この本は昭和50年代の児童向けの小学館入門百科シリーズですから信憑性は低いわけですが、水木しげるは戦後、日本民俗学の大御所・柳田国男が全国各地から民話や伝説を集めたように、怪異現象や不思議伝説を全国から集めイマジネーションを駆使してオリジナルの妖怪を増産したのでしょう。柳田の名著『遠野物語』に大きく関わっている遠野の語り部・佐々木喜善も、同様に岩手県内の語り部たちが語る伝説や逸話を集めていました。そんな背景から宮古の『海女・髪長姫伝説』や『横山八幡宮・神歌伝説』なども吸い上げられ『柳田国男全集』に掲載されているわけです。ちなみに水木が集めた岩手の妖怪は座敷童や河童の他に、かなりマイナーですが田野畑村島ノ越あたりにいたという海小僧(『続・妖怪辞典』掲載)をはじめ、遠野にいたという高坊主などもあります。ところで私が野田周辺で取材しましたところ、蛸神の伝承はすでになく蛸も普通に食べているということでした。

否哉(いやや)
最近はおねぇキャラとして定着か
年中テンションが低く怠け者で、何もせずゴロゴロしていたいという傾向が強い僕なのですが、怠けてばかりではお金も稼げないわけですから、心の奥底は退廃的な風が吹き荒れているのに一応のやる気を見せて仕事をします。今までそんな調子で何十年もやってきたわけですが、今思うとどこからが真面目ゾーンでどこからが手抜きゾーンだか自分でもわかりません。しかも、人生長く生きておりますと全力投球で接した仕事の評価より、半ばほら吹き三味線でなんとなく通過していった仕事の方が評価も実入りも大きかったりすることもあるわけです。
さて、人間誰しも心の中には怠けの虫がいるものです。その怠け精神を引き出して相手を無気力にしてしまうという妖怪がいます。その名も否哉。江戸の妖怪絵師・鳥山石燕は『今昔百鬼拾遺・下之巻・雨』で若い娘の格好をした髭面の男が己の顔を水面に映し悦に入る図を描き「昔、漢の東方朔、怪しき虫を見て否哉と名付けた。今、この否哉もならびて名付けたるべし」と書き込んでいます。東方朔とは漢の武帝に召し抱えられた政治家で、道に伏していた生肝色の虫を見て「いな・や(いやや)」と発したことにあやかり、石燕は気味悪い女装男を描きこれに否哉と命名したと思われます。否哉の着物は桜の花が散った風流な柄に帯が前結びであり、あきらかにその道の商売女の意匠が強調されています。否哉が佇む川面の奥には田んぼなどに水を分ける堰がありその前面に葦が茂っています。従って否哉が出没するのは山間や寂れた山村ではなく、町中に近い場所です。もしかしたら葦や芦を描き込むことで石燕は、江戸の歓楽街・吉原で稼げなくなったお女郎が流れ着く岡場所を描いたのかも知れません。
現代の妖怪絵師・水木しげるはテレビアニメ『ゲゲゲの鬼太郎』の中で女装した中年オカマを描きなぜか「いやみ」という名で登場させています。いやみはその怠けの息を吐きかけ鬼太郎を無気力な怠け者にしてしまうのでした。しかし、否哉の発生の根本には売春のニオイが漂いますから、その後いやみは鬼太郎シリーズには登場しませんし、氏の著書でもいやみが紹介されている本はあまりないようです。近年は性同一障害などという病もあって一概に性的不一致をオカマだのオナベだのとは言えないわけですが、世の中には明らかに奇をてらって商売目的で女装している人もいますし、変態的に女装が趣味の人も少なからずおります。
近年はタレントでも女装をする男性が多くなり美容整形の進歩もあり、下手するとその辺の女性より見た目は美しいという場合もあります。また男の女装は歴史的にも多く、日本では後醍醐天皇が女官に化けて吉野に逃げおおせましたし、源頼朝の娘・大姫の婿さんだった木曾義仲の長男も北条政子らの勧めで女装して館から脱出しています。現代のアニメ文化の中でも否哉的キャラクターは物語の中に必須であり、独特の「おねえ言葉」を駆使してキャラを印象づけます。また、主人公がなんらかの拍子に女に変身したり、階段から転げ落ちたカップルの性が逆転してしまうなどは定番のストーリーとしていつの時代も違和感なく受け入れられます。きっと男は女に、女は男に変身したいという願望は誰の心の中にでもあるということなのでしょう。
妖怪・否哉は、後ろ姿から女だと思って近づき不謹慎な下心丸出しで声をかけたら、なんと、その正体は髭面のオヤジ…。下半身でむずむずしていた元気のいい虫も一気に萎えてしまい、それだけならまだしも、その不気味な顔を思い出すと二、三日仕事も手に付かず飯のくいあげ…。それが否哉の正体なのでしょう。

姑獲鳥(うぶめ)
都市伝説の影にこびりついた姑獲鳥の正体
現代の妖怪絵師でもある作家・京極夏彦氏のデビュー作は『姑獲鳥の夏』という戦前の産婦人科医院をモデルにした怪奇小説でした。僕はこの本を盛岡の本屋さんで買って東京行きの新幹線の中で読みました。推理ミステリー的文庫本なら片道で読んでしまう僕ですが『姑獲鳥の夏』は盛岡~東京往復でも最後まで読めませんでした。それほど難解な小説でした。ところで『姑獲鳥の夏』というタイトルを何人の人が正しく読んで、姑獲鳥が妖怪のことであることを知って本を手に取ったのでしょうか。当時から妖怪オタクだった僕は姑獲鳥が妖怪でありその漢字が日本では「産女」と当てられていることを知っていましたから、小説の舞台が産婦人科医院だったのもすぐ納得しました。
まず姑獲鳥は「うぶめ」と読む他に「こかくちょう」とも読みその先頭の文字「姑」は「しゅうと」と読みます。この文字が当てられていることは重要で、母にとって命より大事な息子を色香で惑わせいとも簡単に奪った嫁に対する潜在的な憎しみが込められています。その憎い嫁とわが息子の間に生まれた子供は孫であり、嫁の憎さなど超越した愛らしさがあふれています。本当はそれを抱いてわが子のように世話したいのですが家では嫁が抱かせてくれません。姑は孫を抱きたいがために夜な夜な外へ出ては幼児がいる家に目星をつけてはさらって自分の子として育てたといいます。これが中国に伝わる姑獲鳥の正体です。姑獲鳥は空を飛び、夜に産着やオムツ(おしめ)を干している家を見つけては毒性のある乳をかけその衣類を着た赤ちゃんを病気にさせるのだそうです。これは汚物で汚れるオムツを太陽の出ない夜に干すこと自体、ばい菌が繁殖して赤ちゃんの肌に悪いわけでこれを戒めるための言い伝えなのでしょう。姑獲鳥の記述は江戸時代末期に日本に渡った中国の百科事典でもある『和漢三才図会』にあり、鴎に似た大型の鳥で里に降りては子連れの女に変じ道行く人に「この子を抱いてくれ」と頼むと記載されています。
子を身ごもり不幸にも亡くなった女の念は凄まじいとされ、昔から成仏しないとされてきました。わが子を抱けなかった女の情念は日本各地で飴買い幽霊、夜泣き石、子育て幽霊など様々な形で妖怪化して姑獲鳥となったのかも知れません。徳島県の山中に出没するという「子啼き爺」は赤子の声で人を近づけこれを抱き上げるとどんどん重くなって最後には人を押しつぶすという妖怪です。姑獲鳥もこれと同様に子を見ず知らすの人に抱いてくれと頼み、どんどん重くなる怪異を呈すわけです。この怪異は重量もさることながら子を抱く責任の重さです。姑獲鳥が子を抱かせる相手の性別は特定されませんが、おそらく男であり生まれてきた子に対する男の責任の重さを問うのだと思われます。
江戸末期の凶作が続いた時代、宮古浦の建網に間引きされた子の遺体がたくさんかかったという言い伝えをはじめ、遠野の民俗資料館には泣きながら幼児の口を塞ぐ母親の影が鬼婆の姿に見える明治頃に描かれた錦絵などもあります。当時、盛岡城下でさえ道ばたに餓死者が転がっていたそうですから山間部では極限の飢餓状態だったことでしょう。そんな時代、貧しい農村部から子供を買い取り手足を数珠繋ぎにして連れていったという人買い・津軽婆っこの伝説も語られ、これが「花いちもんめ」という子取り遊びになったという説もあります。太古の昔から子は宝です。その反面、昔から男女のもつれによる子堕ろし、飢饉凶作による子捨てや人身売買があったのも事実です。妖怪・姑獲鳥はそんな人の歴史のアンダーな部分に潜んでいる闇の妖怪なのです。

箒神(ほうきがみ)
ゴミを掃き集める箒もじきに不要となってゴミになる
何年も使用した物器に使用者の愛情や念がこもりそれが神や霊魂となって取り憑く付喪神(つくもがみ)の怪異は江戸の妖怪絵師・鳥山石燕の『画図百鬼器徒然袋・巻之中』にこれでもかというほど出てきます。それらは子供の頃に天井のシミや洋服ダンスの木目が人の顔に見えたりするのと同じ感覚で椀や鍋釜の生活必需品にはじまり、琵琶や三味線、琴、太鼓の楽器類、葬儀で使う鉦や木魚、僧侶が持つ如意などに目鼻や手足がついたものが妖怪となって描かれています。石燕は室町時代の『百鬼夜行絵巻』などを参考にして自らも想像力を膨らまし独自のアレンジを加え、付喪神たちが夜な夜な歩き回る百鬼夜行登場妖怪の個別カタログとして百鬼器徒然袋を描いています。
そんな付喪神の中に箒神(ほうきがみ)という単なる柄の付いた箒の妖怪が描かれています。石燕は紅葉などの落ち葉が舞う芝垣に庭を掃く竹の箒を立て掛け、ちりとりを置いています。箒の柄の上にはやはり製図やマンガなどを描くときに使う消しゴムカスを掃く羽根箒を描き、その奥に室内を掃く時に使うホウキ草を編み込んだ取っ手下が布などで装飾された室内用の箒を描いています。都合三種類の箒が合体して描かれた箒神は古くなって使い捨てられた箒の付喪神という意味なのでしょう。
石燕は箒神の説明として画面右上に「野わけはしたなく吹けるあした、林かん酒をあたたむ…」と意味深な説明をしています。これは中国の古い詩人・白居易(はくきょい)が秋の朝に林間の紅葉を集めて焚き火をしその火で酒を温めたという風流な漢詩をモチーフにして箒や紅葉を描いたものでしょう。しかしながら、石燕は落ち葉を集め焚き火をで一杯やる風流ではなく、落ち葉のような不要なゴミを集めるために使われる箒でさえいつかは不要になってしまうという使われる物器の悲しさを表現しようとしているようです。
亡くなった昭和ギャグマンガの巨匠・赤塚不二夫のオリジナルキャラに箒を持って道ゆく人に「お出かけですかレレレのレ」と問う着物姿のおじさんがいます。ワンパターンの笑いを誘うギャグキャラですがじつはあれこそが、道を掃き清めいつかは自分も掃き清められる箒神の化身かも知れません。ギャグマンガの裏側にはシュールな現実が隠されているものですね。
ところで僕が少年だった頃ベンチャーズが流行ました。エレキと呼ばれた電気ギターの音は衝撃的かっこよさで日本中がテケテケに染まりました。当時僕より5つほど年上だった従兄弟の姉は雑誌の付録についてきたソノシートで名曲『ダイヤモンドヘッド』を毎日聴いていました。彼女の部屋にあったポータブルプレーヤーからその音が聞こえてくると僕らも負けじと柄の長い箒を持ってベンチャーズの真似をしてテケテケごっこで遊びました。考えてみるとかなり古い時代からエアギターをして遊んでいたわけです。そんなベンチャーズも数年後、絶叫系のグループサウンズへ移り変わり、家にも箒に代わって電気掃除機がお目見えし柄の長い箒はテケテケと一緒にどこかへ行ってしまいました。

ぬらりひょん
身なりやうわべだけで人を判断してはいけません
お店が最も忙しくなる時間帯にどこからともなくやってきて、お店の社長さんの名前を呼び捨てにし「○○はいるか?」などと従業員やお手伝いに問うやたら態度のでかい客人がいます。みればその身なりも上等な服ですし恰幅もいいわけで、人を見抜く歴戦の目利きを誇る番頭でさえ「この方はどこかの御店の旦那様で、おそらく社長とは昵懇の仲なのだろう」と思ってしまい応接間へ通してしまいます。しかしながらあいにく社長は所用で出掛けており、客人には社長が戻るまで待ってもらうことにします。するとあろうことか社長の葉巻に火を着けて、待ってやるから酒とつまみぐらい出せと怒鳴ります。恐縮して簡単なお膳とお酒を用意して応接間に運ばせた直後に社長のご帰宅です。番頭は応接間で待っている客人の風貌を話しますが社長はそのような人物は思い当たりません。それでもそこは商売人、こちらが忘れているだけでお得意様の場合だってありますから、社長さんも恐縮しながら応接間に入ってみると客人の姿はありません。葉巻の残り香と飲み散らかしたお膳があるだけです。「客はどこだ?」という社長の問いに番頭さんは「変だなぁ」と首を傾げるだけでした。そうです、これが妖怪・ぬらりひょんのやり口なのです。セキュリティーの盲点をついて堂々と入ってきて好き放題やらかし煙のように消えてしまうのです。
江戸の妖怪絵師・鳥山石燕は『画図百鬼夜行・前編・陰』で上等な着物に脇差しをさして駕籠(乗り物)から降りてどこぞのお屋敷に乗り込む、ぬう(ら)りひょんを描いています。絵には説明はなく名称の「ぬうりひょん」の「う」は「ら」の誤刻(版木の彫り間違い)とされています。石燕のぬらりひょんは版画で駕籠や玄関などが緻密に描かれていますが、天保の頃(1830~1843)に書かれた尾田某の作とされる巻物『百鬼夜行絵図』にもぬらりひょんが肉筆画で描かれ、こちらは頭皮がぶよぶよした頭でっかちの異形の輩として表現されています。どちらのぬらりひょんも共通して頭髪がない大きな頭で脇差しを持っていますから町人風情よりは偉いイメージであきらかに高飛車で人を騙す雰囲気が漂っています。ぬらりひょんの「ぬらり」は粘液などでぬらぬらしたつかみ所のない様子であり、「ひょん」は突拍子も予告もなしの登場を表します。つかみどころのないというのが得体の知れない、さりとてぞんざいにもできない人物による突然の訪問であることを意味します。
現代の妖怪絵師・水木しげるはぬらりひょんをその恰幅のよさから、人間たちに見放され妖怪化した化け物たちの総大将として位置づけ悪役の親玉としています。しかしその正体は失敗を誰かのせいにしたい責任転嫁の心と、うわべの見た目に騙される目利きの脆さに潜む、単なるまれ人を妖怪化したものでしょう。 宮古市も先頃の市議選挙が終わり一段落しましたが、選挙運動中は誰ともつかない輩が出入りして飯や酒を喰らうものです。てっきり陣営の仲間と思っていたらなんと選挙後、当選したライバル候補のテレビ中継の映像の中に、選挙運動中にやってきてスタッフを大声で叱りタダ飯を食っていったあのオヤジが映っていたりします。ぬらりひょんってある種の貧乏神の化身なのかも知れません。

手の目
手の目の「目」とはサイコロの目だ
若い頃からとめどもなくギャンブルにお金をつぎ込んできた私ですが、実はかなり前から気付いていたことがあります。それは世の中には強運がある人とまったく運がない人がいると言うことです。競馬、競輪、競艇にはじまり、パチンコ、スロット、麻雀、花札、宝くじにナンバーズ、はてはルーレットにトランプ、ダイスにチンチロリンとまぁ、世の中にはあらゆる賭け事が存在します。その中で過去のデータ検証と、無限に近い組み合わせ、確率と第六感、霊感にヤマ感、そして開き直り的直感で人は悩み苦しみギャンブラーは様々な狭間に立たされて疑心暗鬼の世界で自問自答します。そしてほんの僅かな強運者がラッキーチャンスにあやかり、その他の大勢の運のない人々は億万長者の夢だけを見て散財し、その血と汗が染み込んだ利益で博打業界の胴取りは新たな毒花を咲かせるのだと思います。
僅かなお金が一瞬で倍、数倍、数百倍に変わってしまう嬉しさを経験すればもうギャンブルの虜です。そしてその快感を得るためなら多少の過剰投資も惜しみません、誰が止めようが諭そうが馬耳東風。しまいには「趣味」だと開き直ります。大体にして人類の創生期から貝殻や石ころの裏表を当てる博打は存在したと思います。お金などなくても物々交換でさえもギャンブルは可能ですからギャンブルの歴史は人類の歴史と言っても過言ではありません。だから博打で「カマケース/破産(宮古弁)」するのも縄文時代からの伝統とも言えるわけです。
さて、江戸時代のことです。こともあろうに盲目の旅の僧侶を襲ってその懐中から金銭を奪った輩がいたそうです。僧侶といっても乞食坊主も同然だったでしょうから襲って奪うほどの大金を所持していたとは考えられませんが、金を盗まれた僧侶は死んでも死にきれなかったらしくその執念は、両手のひらに大きな目玉がある妖怪・手の目として生まれ変わり懐中を狙った輩を捜し求めて徘徊したのだそうです。
江戸の妖怪絵師・鳥山石燕は『画図百鬼夜行・前編・陽』ですすきヶ原で彷徨う手の目を描いていますがそこには何の解説もありません。また、熊本県八千代で見つかった天保の頃に尾田某の手によって描かれたとされる『百鬼夜行絵巻』という巻物にも草むらに跪き両手のひらに目玉がある盲目の僧侶・手の目があります。
手は人間の感覚器官のなかでもかなり精密で、物を手で触っただけであたかも見える感覚に近い信号が脳に送られますから手はまさしく第二の目であると言えます。しかし、それでは盲目でなくとも麻雀牌を親指の腹で触ってその牌を見ずに当てる盲牌と同じです。そこで私は妖怪・手の目とは犯人を見つけて恨みを晴らそうとするが故に手に目玉がついたのではなく、博打に目がない(盲目)ほど好きで好きでたまらない男が死んでもなおサイコロ博打をやりたくて彷徨う哀れを表現したものではないかと思います。目とはすなわち「出目」「当たり目」「買い目」です。博打の儲けで蔵が建ったためしはありません。蔵が建つほど当ててもそれを同じぐらい博打で散財するのが常です。汗もかかず苦労もしないで手にしたお金には実感と愛着が欠如しているのです。だから人は儲けた金をさらに大きくしようとして簡単に失敗します。きっと競馬場やパチンコ店をはじめ東京証券取引所あたりにはネクタイを締めた妖怪・手の目がたくさんいるのだと思います。

天井下(てんじょうくだり)
天井下(くだり)と天井嘗の関係
近年の住宅は内装材が進歩して部屋の中も明るく清潔な雰囲気です。壁は俗にクロスと呼ばれる壁紙を貼って木造家屋なのに地中海の白壁の家のようです。それに合わせて天井も生成色のクロスに柔らかい間接照明…。
戦後の焼け野原に建てたバラック小屋から見れば現在の日本人の家はお殿様の城の域です。しかし、そんな近代的文化生活となっても家の中には様々な異界があるのも事実です。家によっては先祖の位牌を入れた仏壇や八百万の神仏を祀った神棚もあるかも知れませんし、毎年大晦日が近くなれば便所や流しにしめ縄をかけたりもして、文化生活を営んでも人はいつの時代も目に見えない何かの存在を意識しているようです。
そんな私たちが暮らす家の中で最も異界とされるのが天井裏です。日本建築の中でいつの時代に天井という概念が発生したのかは判りませんが、私たちの住居形態は直接地面のワンフロアだった竪穴式住居からスタートして、後に壁と天井で空間を仕切るプライベートな部屋が作られるようになりました。天井裏という空間は私たちが暮らす平常空間のすぐ隣にありながらめったなことでは目にすることはありませんし、まして忍者のように入り込む空間でもありません。そのため昔から天井裏に鬼が棲んでいたり死体が散乱していたというような話が語られてきました。延宝5年(1677)に刊行された『宿伊草(とのいぐさ)』二巻では「甲州の辻堂に化け物ある事」で天井が安達ヶ原のような死体が散乱する場所であると語り、「三人しなじな勇ある事」や「古堂の天井に女を磔にする事」では姦通する妻と間男を見つけた夫が間男を斬首し、妻はその首を抱いたまま天井に監禁されたことを伝えています。
江戸の妖怪絵師・鳥山石燕は『今昔画図続百鬼・巻之下・明』において天井からぶら下がる天井下(てんじょうくだり)を描いて、脇に「昔、茨城童子は綱が伯母と化して破風をやぶり出て、今この妖怪は美人にあらずして、天井より落。俗世の諺に、天井を見せるというは、かかるおそろしきめを見することにや」と書き込んでいます。これは天井を見せるという動作が人を困らせるという意味で、私たちも思案に暮れたときに天井を見たりするものです。茨城童子とはその昔、京都を荒らし回ったとされる酒呑童子の家来で渡辺綱と戦った鬼の一人です。また石燕は『画図百鬼徒然袋・巻之上』で床下から湧き上がって長い舌で天井を舐める天井嘗(てんじょうなめ)も描き「天井の高は灯くらうして、冬さむしと言へども、ぞっとするなるべし…」と書き込み部屋の天井が高いと僅かの明かりでは頭上は暗闇だと語っています。現代の妖怪絵師・水木しげるは旧家の天井にあるシミなどは天井嘗が舐めた跡ではないか?と解説しています。いずれにせよ天井が異界であることには変わりありませんし、マンションなどでは階下にとっての天井は階上の床下ですからその空間は妖怪が棲む異次元なのかもしれません。階上で暮らす人から見れば天井嘗で階下で暮らす人から見れば天井下(くだり)なわけです。

赤舌(あかじた)
水を盗むと火事の時水に困るという戒めか
太陽系の外に浮遊している小惑星に着陸してその表面の欠片を地球に持ち帰るような科学万能の時代になっても日本人は日の忌みを嫌います。迷信と思っていても出船や婚礼は大安吉日を選び、死者が続くからと友引の葬儀は嫌われます。ほとんどの人はそんなの気にすることはないと普段は口では言いながら、やはり厄日とされる日を避けて事を運ぶものです。そうかと言えば、カラスの啼き方がおかしかったから不幸の知らせが届く、妊婦が葬式に出ると良くないなどの言い伝えから、葡萄や枇杷を庭に植えると病人がたえない、柊や南天を植えると厄を祓う、漬けた梅干しが腐る年は天候不順が続く…などなど、迷信を挙げればきりがありません。これらは大陸の道教に準ずる膨大な占い術の集大成から得たデータをもとに語り継がれたもので、当たる当たらないではなく確率が高いという示唆にすぎません。だから本当に不幸になる場合もありますし、むしろ何も起きない事の方が多いと思われます。
さて、少子化が進む昨今ですが、その昔、昭和22~24年の第一次ベビーブームのあと一度は減少に転じた人口が、昭和46~49の第二次ベビーブームに向かって増えたにもかかわらず昭和41年だけ極端に出生率が落ち込んでいるというデータがあります。なんとこの年は生まれた女の子はじゃじゃ馬娘になるという迷信がある、丙午(ひのえうま)だったのです。太平洋戦争が終わり約20年の歳月が流れ、高度成長期に好景気でバイタリティー溢れる時代であったにもかかわらず昭和40年、お父さんお母さんの夜の営みは丙午迷信で開店休業だったわけです。江戸末期に爆発的に流行った庚申信仰では、やはり庚申の日に交わって生まれた子は火つけになると信じられていましたし、夜方面の秘め事は各地方によって様々な迷信が存在しそうです。
さて毎度お馴染みの江戸の妖怪絵師・鳥山石燕は『画図百鬼夜行・前編・風』で田んぼへ水を入れる堰の板を開けて水を流している所へ黒雲とともに現れ大きな口を開けてベロを出している毛むくじゃらの妖怪を描き赤舌(あかじた)と記しています。説明はないのですが隠れて我田引水をすると何者かに戒められることを示唆しているようです。おそらく石燕は化け物のベロや胴など墨版のベタ部分を真っ赤なイメージで描き赤舌としたのでしょう。水と対比する赤い舌とは炎のことであり、水を盗んだ者に火の戒めがあり、隠れて水を盗むと自宅が火事の際に消し止めるための水に不自由すると言いたかったのでしょう。
ちなみに関係あるかどうか判りませんが日めくりの暦などに表記される赤口は、陰陽道に関係し、太歳神(木星)の西門を守護する赤舌神(しゃくぜつしん)を意味します。陰陽道ではこの日を「しゃっこう」とか「あかぐち」と言いい万事に凶という運勢の日だとし、僅かに正午だけを吉としています。最後にちょっと未来の話ですが、次の丙午は西暦2026年です。あと16年後、日本は今より国際化しているでしょうがきっと出生率が落ちるでしょう。いくら国際化してもきっと迷信、妖怪、オカルトは不滅なんだと私は思います。

鳴釜(なりがま)
穀物を蒸す甑(こしき)が発する異音が正体か
私が子供の頃は長屋というか、飯場というか大きな民家を何戸かに仕切ったような複数世帯統合型住宅がけっこうありまして、長屋に住む人たちは風呂やトイレが共同ですから運命共同体のような暮らしぶりでした。そんな長屋の子供たちが集まって「はないちもんめ」という遊びをやっていました。この遊びは交互に唄を歌って前後移動し欲しい子を決めたらジャンケンで奪う単純なルールです。温厚なイメージですが内容は相手側から人を奪うもので、飢饉の時に食い扶持を減らすために子供を売った背景があるとも言われています。このはないちもんめの歌詞の中に次のような部分があります。
A「隣のおばさんちょいと来ておくれ」
B「鬼が怖くて行かれません」
A「お釜を被ってちょいときておくれ」
B「お釜がないので行かれません」
と言うものです。当時は何気なく聞いていたのですが、お釜を被るという行為と鬼の存在が不気味です。古来より釜で湯を沸かしそこへ神霊を降ろす湯立てという神事がありますし、釜の底にこびり付いた煤を魔除けとして生後間もない幼児のおでこに塗ったりします。お正月の羽子板遊びの罰ゲームで使われる墨汁も本来は釜の煤だったと思われます。また、子供の頃は釜や鍋、カゴやザルを頭に被ると背が伸びないといわれました。鍋や釜は湯を沸かし神霊が降りる依り代なわけでこれを被るというのは罰当たりなことだということで背が伸びないなどの迷信が生まれたのでしょうか。
江戸の妖怪絵師・鳥山石燕は『画図百鬼徒然袋・巻之下』に羽釜を被った毛むくじゃらの化け物が絵馬を捧げる鳴釜を描き、右上に漢詩を書き込んでいます。これによると大陸の黄帝がすべての化け物を知るという白沢(はくたく)という妖怪から聞き及んだ情報を元に、絵師に鳴釜を描かせたとしています。石燕は左上に火の入っていない竈を、鳴釜の前におそらく蒸缶と思われる特殊な形状の道具を描いています。
元々鳴釜とはその文字が示すように、釜が鳴る怪異と思われます。しかし釜は単に熱しただけでは音を発しません。ではどうすれば釜から音が出るかということになります。そこで登場するのが釜の上にのせて穀物を蒸し上げる甑(こしき)です。甑は弥生時代からある道具で土器で作られましたが大和時代末期には木製の蒸し器に置き換えられ土器製のものはなくなったようです。穀物を蒸して搗いたものが餅でありやはり神霊に捧げる大切な供物でした。甑は中央部が膨らんだ円筒形の道具で、中央の膨らんだ部分に穀物を置く州があります。これを湯が沸騰した釜の上にセットして上部に重い蓋をします。蒸気は甑の中を対流しながら穀物を蒸し上げ同時に対流と振動によって本体自体から音を発します。この低音が鳴釜の怪異であり、この音の音色や大小でその年の作況を占うこともあったようです。後年は円筒形の甑は方形の蒸籠(せいろ)に変化し鳴釜現象も忘れ去られました。ちなみに岡山県岡山市の吉備津神社では釜を鳴らして吉凶を占う鳴釜神事が今も行われ多くの信仰を集めているらしいです。

山童(やまわら)
山童はデンデラ野に捨てられた異形の者であったか
山童(やまわら)という妖怪がおりまして、関東から北ではあまり馴染みがないのですが西日本では河童の山版としてメジャーな妖怪なのだそうです。山童は人がいないのに木を倒すという天狗倒しや、不思議な山びこなどの山の怪異を引き起こす妖怪とも言われております。私は言わずと知れたズーズー弁満載の東北人ですから子供の頃は山童という妖怪にはあまり惹かれませんでした。そのため大人になっても山童発生の背景やその推測の展開などあまり気にしておりませんでした。しかし、山童の発生背景には柳田国男らも盛んに論じていた山人説や、姥捨てなどで捨てた老人や不虞者なども山童に関係しているような気がします。
信州の寒村に住む人々を描いた姥捨がテーマの深沢七郎作の小説『楢山節考』は三島由紀夫も絶賛し映画やドラマにもなりました。そもそも姥捨ては食べるだけで労働力にならない老人が自ら深山に捨てられることを望むもので、家の存続と他の家族が生きるためやむなく老人を捨てる風習でした。現代社会なら会社が他の従業員のため長年勤め上げてきた社員に幾ばくかの退職金を与え定年にするのに似ています。さて、そんな姥捨てに関する伝説は『遠野物語』にもでてきますし、川井の伝説にも出てきます。川井の伝説では捨てに行った爺様を捨てずに連れて帰り家の縁の下に隠しておく話ですし、遠野の話は蓮台野(でんでらの)に捨てられた者が農繁期に手伝いにくるというようなイメージです。
私はかなり前から蓮台野に捨てられたのは老人ばかりでなく、病気持ちや不虞者はもちろん村に居ては都合の悪い人間だったと考えています。彼らは隔離された世界で暮らしたまには里に降りては悪さもしたでしょう。山爺や山姥の怪異は捨てられた人々が想像もつかない変わり果てた姿となり、木樵や猟師が山で遭遇してしまう状況が生んだ妖怪かも知れません。さて、捨てられたのは老人だけでしょうか?私は常々、生まれてはいけない子供や、生まれながら世をはばかって生きねばならぬ子供らも神隠しと称して蓮台野へ遺棄されたと考えております。狭い寒村では人と違うスキャンダルや噂は命取りです。代々噂は消えず、しまいには狐だ鼬だと憑き物扱いされ村八分となりその家は婚姻も叶いませんから将来は没落します。
毎度お馴染み江戸の妖怪絵師鳥山石燕は『画図百鬼夜行・前編・陰』で山童を描き、やまわらわとルビをふっています。石燕は『化物づくし』(作者不明)を参考に一つ目で河童のように頭に禿がある毛むくじゃらの人型の妖怪を描いています。ちなみに中国の博物百科事典でもある『三才図絵』を見本に大阪の医師寺島良安が編纂した『和漢三才図絵』には「やまわろ」として掲載があり「九州の深山におり、童顔、全身細毛に覆われ、脚は細く、人語を話す」と説明があります。
数年前人気を博したアニメでありドラマにもなった、金田一少年の事件簿の『秘宝島殺人事件』にも財宝の祟りの象徴として山童が登場しました。河童の山版とは言え、どうしても山童は河童のようにメジャーにはなれず不気味な山の怪異としてのイメージが拭えないようです。

朧車(おぼろぐるま)
賀茂祭の頃、朧月の夜に現れる百鬼夜行の怪異
古典文学の最高峰でもある『源氏物語』葵ノ巻に「車争」という件(くだり)があります。すれ違いができそうにない狭い道路で、対向車に対して「お前が下がれ」「こっちが優先だ」と自己主張するようなもので、あたかも東海地方にあるという花嫁道具を積載したトラックが絶対にバックしないという縁起担ぎの発端になったような物語でして、おおまかには次のようなストーリーが展開されます。
賀茂祭の御禊(賀茂斎院が加茂川の河原で禊する)の日、光源氏も供奉のため参列することになりました。その情報を得た光源氏の元カノ・六条御息所は、この頃さっぱり寄りつかない愛おしい光源氏の姿をひと目見ようと身分を隠し牛車を仕立て出掛けました。ところがその当時、懐妊し体調が良くないので単なる気晴らしついでに見物に立ち寄った光源氏の正妻・葵の上の牛車と鉢合わせになってしまいました。両陣営は一般の見物人で溢れかえる都大路の真ん中ですれ違い出来ず進め戻れと争いを起こしました。この時代は道を譲ることは相手を位の高い人物として認めることと同様だったようで、高ビーでセレブな女二人は多情な色男・光源氏のこともありヒステリー状態だったわけです。結末は葵の上の一行の牛車が時の権力にまかせた乱暴によって六条御息所の牛車を蹴散らしました。これにより六条御息所の牛車は大破し一般の見物人であふれる一条大路で大恥をかかされてしまいました。大臣の娘で元東宮妃である六条御息所にとってこれは耐え難い屈辱で彼女は葵の上を深く恨みました。
その後、葵の上は原因不明の病の床についてしまいますが、なんとそれは六条御息所の生霊の仕業でした。光源氏も苦しむ我が妻・葵の上に付き添って看病に努めますが、六条御息所の生霊を目撃してしまい愕然とます。葵の上は難産のすえ男子(夕霧)を出産しましたが産後の肥立ちが悪く容体が急変し死亡します。ちなみに光源氏は正妻の四十九日が済んだ後、二条院に戻り美しく成長した紫の君(血縁じゃない?)と密かに結婚します。いくらお盛んでも生霊と化した女の所へは戻るはずはありません。
六条御息所はその後も生霊となって光源氏が愛でる女の側に現れては恨み辛みを語り続けるわけですが、その後伊勢に下り出家し病気で亡くなります。しかし、またもや今度は本物の死霊となり光源氏の正妻となった紫の上やその娘に取り憑き本格的に悪霊となります。そんな六条御息所がプライドを傷つけられ嫉妬と怨念に身を焼いた賀茂の大路には、おぼろ月の夜に何処からともなく牛車の音が聞こえ、霊が彷徨うとされます。牛車の蔀(しとみ)の向こうには恋に狂って異形の者と化した六条御息所が座しているのでしょうか。
妖怪絵師・鳥山石燕は『今昔百鬼拾遺・中之巻・霧』において霧にむせぶおぼろ月に点線描きで牛車を描きそのすだれの奥に髪を乱した大顔の鬼を描いています。『宇治拾遺物語』という本に賀茂祭の夜、遊女と寝ていた男が大路を過ぎる百鬼夜行を目撃した話があり、賀茂祭見物と鬼は何かと縁がありそうです。

雨降小僧
暴風雨の中、増水した河川を見回る水神の化身か
俗に沿岸漁師はお尻が痒いとイワシが大漁すると縁起をかつぎ、妊婦が葬式に出る時は懐に鏡を入れろとか、死人に家猫を近づけてると死霊が取り憑いて踊り出すなどなど、迷信や俗信にも色々なものがありますが、これらは大陸で数千年がかりで積み上げられた道教の膨大なデータを元に割り出した偶然性の確率が高い事例を八卦や占いレベルで伝承したもので確たる根拠はないようです。それでも人は大安吉日に宝くじを買い、近所や親類に不幸があると「どうりで最近カラス啼きが悪かった」などとこじつけたりするものです。さて、そんなたわいもない迷信のなかに、その花を摘むと必ず天気が崩れるという雨降り花の迷信があります。
私が初めて雨降り花という名を耳にしたのは小学校三年生の頃でした。学校から帰っていつも遊んでいる神社へ行くと友人が「今日はこの神社の裏道を行けば何処に着くのか行ってみよう」と言うのです。神社の裏は鬱そうっとした杉林で道は山の奥へと向かっていました。私たちはその道を進みいくつかの尾根を超えてやっと人家のある所へ出ました。時間にすれば一時間程度でしたが森の中で方向感覚が喪失し同じ所をぐるぐる回っている感じでした。私たちが出たところは自分たちが住んでいる振興団地の外れにある古い民家の裏山の斜面でした。そこには真っ白い花がいっぱい咲いていて別世界のような美しさでした。お尻で滑るようにして斜面を降りるとオバサンがいて「あの花は雨降り花で、取ると必ず雨が降るんだ」と教えられました。私たちは花を摘まなくてよかったな、と語り合いその家を後にしました。
雨降り花とされるホタルブクロを摘めば何らかの事象が発生し天候が崩れ雨が降るはずなど到底ないのですが、雨が降り出す寸前の薄暗く湿度高い空気の中でホタルブクロの白い花が異常にキレイに見えてつい手が伸びて摘んでしまうということなのだと思います。調べてみますと雨降り花とされる花はホタルブクロの他にヒトリシズカやニリンソウ、ムラサキケマンなどの植物でどれもが梅雨時に白や薄紫の花を付ける花たちです。六月から七月のしっとりと濡れた森に咲く花に目を奪われつい折ってしまうのは人のサガゆえでしょうか。
さて、江戸の妖怪絵師・鳥山石燕は『今昔画図続百鬼・巻之中・晦』で雨の中、破れ傘を被り小田原提灯をさげて歩く、雨降小僧を描き左肩に「雨のかミを雨師といふ。雨降小僧といへるものは、めしつかはるる、侍童にや」と書き込んでいます。雨師(うし)とは中国の雨の神であり、雨降小僧は神の脇に控える侍童ではないのか?と問いかけ団子っ鼻の少年の妖怪を描いています。雨降小僧は雨が降りしきる人気のない晩に出歩き増水して流れが速くなった川や池をみて廻る、言わば水神のようなものかも知れません。

小豆研(あずきとぎ)
マヨヒガ伝説と深山の怪異
深山の奥のまた奥の人がめったに足を踏み入れないような場所に一年中温暖な気候で、果物や穀物などがたわわに実り、鳥獣群れ遊ぶ夢のような桃源郷があるのだそうです。そこは人の望むすべての夢や理想が叶えられた極楽であり人が死に至る直前に見える異空間なのでしょうか。柳田国男の『遠野物語』に登場する深山の長者屋敷、鳥山石燕の『画図百鬼夜行』に描かれる鼠浄土などもこれらの類と思われます。
『遠野物語』では小国村と金沢村の山塊にあるという長者屋敷の怪が『マヨヒガ(迷い家)』として紹介されています。それによると道に迷った杣人が山奥に突如現れる大邸宅におののきながらも家の中へ入って行きます。そこは畜舎に牛や鶏が飼われ、家の炉には火が入り、台所には湯が沸き、祝宴の準備がなされているのですが人がまったくいません。杣人は怖くなりますが証拠の品として朱塗りの椀を盗み屋敷を後にします。当然ながらその後その話を聞いた者どもが屋敷を探すのですが見つかりません。また、屋敷から持ち帰った椀が幸運を呼んで杣人が金持ちになったという後日談もあります。
マヨヒガの話が伝わる小国村(現宮古市)と金沢村(現大槌町)は古くから砂金による産金があった場所でこの地方の金は平安期には奥州藤原氏にも献上されていました。砂金取りは山奥の沢に小屋をかけ秘密裏に行われておりその産出量や規模は記録にも残されていませんし、どこの誰がどんな仕事に携わっていたかもわかりません。そんな産金に携わる人々が住んだ屋敷が長者屋敷やマヨヒガだったかも知れません。いつの時代も山は人を惑わす素材であり、同時に人を隠しえる素材でもあります。山を知り尽くしたはずの杣人や猟師が惑わされ、不要になった老人がデンデラ野に捨てられ、何らかの事情で人の目を忍ぶため奥山へ隠れた人が山人と化します。山は怪異の宝庫であり県土の大半が山である岩手県は怪異そのものです。
深山渓谷を求めて分け入った盛岡の釣り師が上米内周辺の某沢でジャキジャキという異音を聞きあわてて引き返したそうです。おそらく「あずき研ぎ」「あずき洗い」と呼ばれる音の怪異でしょう。この怪異は江戸時代から伝わる割とメジャーな深山の怪で、異音は狐狸のたぐいや蝦蟇が背中をこすり合わせて出すとも言われます。妖怪としては水木しげる氏の『ゲゲゲの鬼太郎』にも登場し背を屈めた法衣の小人が曲げわっぱで小豆を研ぐ姿で表現されます。この姿の原型は天保12年に著者・桃山人、絵師・竹原春泉で刊行された奇談集『絵本百物語』に描かれています。それによると、越後国の高田(現新潟県上越市)の法華宗の寺にいた日顕(にちげん)という小坊主は体に障害を持っていましたが物の数を数えるのが得意で、一升枡の小豆の数もピタリと勘定できました。寺の和尚はゆくゆくは日顕に寺を継がせようと考えていましたが、それを妬んだ同門の円海(えんかい)という坊主が日顕を井戸に投げ込んで殺害しまた。以来、日顕の霊が夜な夜な雨戸に小豆を投げつけ、夕暮れ時には近くの川で小豆を洗って数を数えるようになったのだそうです。
柳田国男は『妖怪談義』でアズキトギとして取り上げ、この妖怪が出没する場所は決まっていてどこにでも出るわけではない。大晦日の晩だけ出るというところもある。西は中国、四国、中部、関東、奥羽におり、いない所はほとんどない。「お米研ぎやしょか、人取って食いやしょか、ショキ、ショキ」という小豆研ぎの怪が口にする文句の分布もかなり広い。と民俗調査を元に断言しています。恐るべし先駆者、柳田…。

海座頭(うみざとう)
モノノ怪登場を思わせる琵琶の音色
岩手の妖怪と言えば真っ先に思い浮かべるのが座敷ぼっこ、こと座敷わらしと遠野をはじめ県内全域の河川にいるという河童でしょう。この他の妖怪は山姥とか鬼ぐらいかな?と思ってインターネットで検索してみますと某サイトに岩手の妖怪として聞いたことのない様々な妖怪の名前が掲載されています。それらを見ますとどこまでが妖怪でどこからが怪物(もののけ)で異人や稀ビトなのか境界線がはっきりしておらず、様々な文献に書かれいる怪異をひっくるめて妖怪としているようです。およそこれらは岩手でメジャーになっている妖怪ではなく明治から昭和初期にかけて岩手、いや当時は陸奥や陸中国を知る語り部が帝都で語りそれが岩手の妖怪として位置づけられ、後年になって岩手に逆輸入されたものです。そんな里帰り的な岩手の妖怪に、海座頭という盲目の琵琶法師の妖怪がおりまして陸中国では海坊主、船幽霊と並んで漁師たちに恐れられていたのだそうです。海座頭は袋に入れた琵琶を背負い座頭独特の杖で探るような仕草で荒れた海の波間を彷徨います。そして漁をする船に近づき「月末は船を出すな」と戒めて船を沈めるのだそうです。しかし、そこまでリアルな言い伝えの割に古くから漁業で栄えてきた私たちの宮古にはそんな伝説も逸話もありません。おそらく海座頭は源平合戦を謡(うたい)で弾き語りする盲目の琵琶法師がモデルと思われますが、古来から陸中国には琵琶法師の謡を理解するほどの人物はおらず、まして漁師らの伝説として残るにしても琵琶という楽器は高尚すぎます。
毎度お馴染み江戸の妖怪絵師・鳥山石燕は『画図百鬼夜行・前編・陽』において琵琶を背に波間に立つ海座頭を描いています。そこに説明はなく杖で足元を探り、耳と鼻に神経を集中させている座頭独特の描写が絶妙です。また、海座頭は熊本県八代市の松井文庫所蔵品の江戸時代のおばけ本『百鬼夜行絵巻』の絵巻にも同様の姿で掲載されることから当時、石燕がこの図を参考にした可能性もあります。現代の妖怪絵師・水木しげるは琵琶を背中にかついだ姿で杖を持って海上に現れる盲目の巨人とし船を沈めると説明しています。
近年は2000年にフジテレビ系深夜のホラーアニメとして放映された『怪・ayakashi』の続編で放映された『モノノ怪』において「海坊主」編に魚が着物を着て琵琶をかき鳴らす姿で海座頭が登場しています。ここでは嵐の海上を彷徨う船の中で乗船客に対し海座頭は「お前の一番怖いもの何だ?」と問いかけその答えに応じて幻影を見せ、そのグロテスクさで嘔吐してしまうというものでした。ま、考えてみれば船に船酔いはつきもので、船酔いに嘔吐もつきものですから無関係とはいえません。
明治から大正にかけて発動汽船が登場し日本の船舶航海は大きく飛躍しました。なにせそれ以前は推進力を風に頼った帆掛け船でしたから航海は風まかせ、定期航路など夢のまた夢でした。例えばそんな時代にザトウクジラなどが繁殖期に行う海面打ちの仕草に出会ったなら漁師たちはそれを海坊主や海座頭の怪異としたでしょうし、セイウチ、オットセイ、トドなどの海獣と遭遇すればやはり海坊主などの怪異としたでしょう。月末に船を出すなという戒めは口開けなどの漁業協定を破った者への戒めだったかも知れません。海座頭…。未だその詳細は不明のままです。

うわん
古寺、古屋敷の怪は野良猫の威嚇であったか
私は貸本マンガばかり読んでちっとも読書しなっかたのですが水木しげるの『妖怪なんでも入門』や、佐藤有文(故人・怪奇作家・オカルト研究者)の『いちばんくわしい日本妖怪図鑑』などはよく読みました。当時の男の子はとにかく図鑑が好きでしたから、私にとって自分の好きな分野の妖怪の絵がズラリと並ぶ妖怪図鑑は毎日見ても飽きませんでした。朱と黒の二色刷で表現される魑魅魍魎や妖怪の絵は恐怖と興味が混同し、少年時代の僕の想像力を大いにかきたてくれました。当時は印刷における写真製版の技術も低かったのですが、昆虫や鳥や魚の図鑑にしてもとにかく写真ではなく人が描いた緻密な絵だったからこそ迫力があったのだと思います。子供の頃に手垢まみれにしたそれらの本は遠い過去に傷んで捨ててしまいましたから、最近は上京ついでに中野あたりの有名マニアショップや神保町の古書店などで発掘しては、昔読んだ妖怪図鑑などを買ってきて会社の本棚に並べております。
さて、そんな妖怪図鑑の中に「うわん」という妖怪が紹介されています。水木しげるの著書『妖怪なんでも入門』などによりますと、うわんは里の妖怪に分類されており、人の住んでいない古屋敷の脇を通るといきなり「うわん」と気味の悪い声を出して通行人に冷や汗をかかせる…。としており、佐藤有文の『いちばんくわしい…』の説だと荒れ放題の古寺の脇を通って不意に「うわん」と声がしたら即、「うわん」と応えないと墓地に引きずり込まれる…。としています。
妖怪・うわんの発生は江戸時代中期の画家・佐脇嵩之(さわきすうし)による妖怪絵巻『百怪図巻(ひゃっかいずかん)』(元文二年1737年)で肉筆画が紹介されており、毎度お馴染みの江戸の妖怪絵師・鳥山石燕はこれを参考に『画図百鬼夜行・全編・風』で崩れた土塀と枝振りのよい柳を描き、柳の木から湧き出るように入道型のうわんを描いております。
石燕がお手本にした佐脇嵩之の『百怪図巻』のうわんは妖怪本体しか描かれていないため、石燕はアレンジして崩れた土塀や柳を書き足したのでしょう。しかし、『百怪図巻』のうわんは大きく開けた口に鉄漿(お歯黒)をさしていますから既婚の女の化け物として表現されているのに、石燕のうわんにはその特徴は排除されています。それでも本家のうわんに習って、うわんの指は三本で表現されこの妖怪が鬼であり、人としての五徳を欠如した成仏を望まない存在であることを意味します。また、古屋敷に枝を広げる樹木が柳であることには意味があり、柳が古くは追善供養の墓に立てる卒塔婆の材料となる木だからです。柳が死者と縁がある木であり、丸山応挙らが描く幽霊画の柳と幽霊もこれが由縁です。
江戸の絵師たちもうわんについて何も解説しておらず、現代の水木、佐藤両氏の解説もほとんどが図鑑に載せるために作者が創作したものでしょう。うわんの正体、それはもしかしたら廃墟に住みついた野良猫2匹がお互い威嚇するために「う、う…、わにゃん!」と吠えただけかも知れません。きっと「幽霊を捕まえてみれば枯れ尾花…」なのでしょうね。テスト