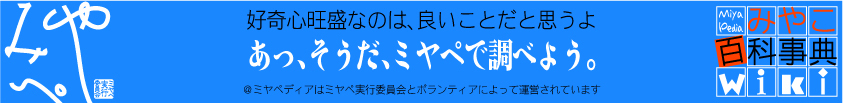南部鼻曲り鮭
目次 |
宮古の魚・鮭
津軽石のさけます人口ふ化場で増殖された鮭は毎年市内各河川から放流され親潮を北上、遠くベーリング海、アラスカ海で生活し3~4年のち産卵のため生まれた川の水を求め南下、10月頃から市内各河川に戻ってくる。成魚の雄は産卵期が近づくと鼻が独特なカギ状に曲がるので「鼻曲がり」の名がある。宮古地方ではこの鮭を塩引きして、新巻鮭として正月に食べる習慣がある。また、鮭は頭から尾、骨に至まで全ての部分を食用にし、その料理法はかなりのバリエーションがある。メス鮭はお腹にイクラ(腹子)を持って おり海のルビーとして宮古地方の珍味のひとつである。イクラは塩で味を付けたものとしょう油漬けがありどちらも美味。とくに炊きたてのご飯にイクラをたっぷり載せたイクラ丼は宮古名物のひとつでもある
悪人か、善人か?ふたつの又兵衛伝説
又兵衛伝説は語られた時代背景により形を変えている特殊な伝説で、一説では鮭を盗んだ又兵衛という浪人を留めの者どもが撲殺。しかしその翌年から鮭は遡上しなくなり稲荷神社で神宣を得たところ又兵衛の祟りと託宣され以後、又兵衛を鮭漁の神として奉ったところ以前のように鮭が遡上したという。また、一説では領内が飢饉で苦しんでいる時に代官所の許可を得ずに留めを解放し村人に鮭を捕らせたため、その罪で死罪となった又兵衛を義民、鮭漁の守り神として奉ったという解釈のまったく違う悪人・善人の二説が語られてきた。これは江戸後期の飢饉や江戸末期の三閉伊一揆などの影響が口伝の中に混同し様々な形として現在に伝わったものと考えられる。また、藩政時代の津軽石川の瀬の権利は津軽石以外の商人が持つこともあったため、目の前に鮭がいても村人は手を出せないということもあったようだ。
毎年鮭漁の季節である11月下旬になると又兵衛祭りと称して神事が行われる。その後川留場の川原には又兵衛を象徴したわら人形が漁期が終わる翌年の3月までかかげられる。
又兵衛まつり
津軽石鮭繁殖組合では毎年鮭漁の季節である11月下旬になると、大漁と漁期の安全を祈願して又兵衛祭りの神事を行う。神事は毎年鮭まつりの会場となり、鮭の直売所がある稲荷橋下の留場で行われ、川原には又兵衛を象徴するわら人形が掲げられる。この人形の形は鮭であり、逆さに磔された又兵衛であるとも伝えられる。河原での神事を終えると関係者らは、津軽の汗石を祀ったという伝説がある岡田恵比寿堂、月山神社、閉伊崎の黒崎神社を参拝し大漁と安全を祈願する。
鮭だ!!ハナマガリ
独特のリズムと歌詞に折り込まれた宮古弁の「ラップ」で不思議と耳に残る『鮭だ!ハナマガリ』はみやこ夏まつりで踊る曲として作詞作曲、編曲、演奏、録音まで市民の手作りで平成7年制作され同年CD化した。現在はシートピアなあど売店で販売されている。
- 唄:木村和秀
- 作詞:横田あきら
- 作曲:三上のりお
- 編曲:吉田俊光
- 三味線:山根美恵子
- 和太鼓:佐々木清
- 振付:前川三男
- 掛け声:木村泰成・佐藤良樹・杉下祐・佐々木敦史・田代貴久
鮭だ!!ハナマガリ・宮古の鮭は日本一
- ヨ~!
- サケと美人といい男
- ハ! みんなおでんせ、おへぇれんせ
- ハ! ソラソラソラ、ソラソラソラ宮古の鮭は日本一!
- ハアー 鼻曲がり鮭 ハアー 鼻曲がり鮭
- 弘法大師も鞭牛和尚もまたべえ様にも忘れちゃいけねぇ恩返し
- 今日も大漁 宮古の鮭は
- ハアー 鼻曲がり鮭 ハアー 鼻曲がり鮭
- 縄文人から現代人まで新巻、中骨、切り身に鮭汁 食べている
- maid in Miyakoの しょっぱい鮭を
- ギンケにブナケも跳ねている
- みんな旨いよ 味がある
- 炊きたてごはんに ハラコをどかんと
- 海のルビーだ イクラ丼
- 朝から晩まで毎日鮭で
- とーちゃんのツマミも サケ、サケ、サケ、サケ
- ギンケにブナケも跳ねている
- ハアー 鼻曲がり鮭 ハアー 鼻曲がり鮭
- 沖のかなたに祝いのフライ旗網元、船頭、網人に大棒、踊ってる
- めでたい知らせだ 今夜も飲もう
- 赤島、須久洞、三丁目
- 定置もいろいろあるけれど
- 閉伊崎かわして一直線
- 目当ての母川かぎ当てる
- 目指すは宮古だ生まれた川だ
- コゲラ散らして サケ、サケ、サケ、サケ
- 赤島、須久洞、三丁目
- ハアー 鼻曲がり鮭 ハアー 鼻曲がり鮭
- ハアー ヨイトコラサ、ヨイトコラサ
- ハアー 宮古の鮭は日本一!
- East bay studio
鮭つかみどり
毎年正月に津軽石川河川敷特設会場で行われる冬場観光の目玉企画。川を塞き止め捕獲されたばかりの鮭を放し、一般参加者に「つかみどり」させるというもの。毎年、満員大入りで入場券売場は黒山の行列となる。近年ははらこそば早食い競争、イクラのすくいどりなどのサブイベントも行われている。沿岸各河川では毎年11月頃からお正月にがけて津軽石川の他に、大槌町など鮭が遡上する川で鮭関係のイベントが開催されている。
津軽石鮭番屋
津軽石川でサケ漁を行っている「津軽石鮭繁殖保護組合」には河口付近に魚舎と呼ばれる番屋がある。魚舎の前の川には留網が張られ、15人の組合員がサケ漁期の時に寝泊まりしながら作業を行っている。
番屋はサケ漁が始まる9月から2月までの期間、開けられる。朝8時からの水揚げに始まり、サケの採卵などの作業に日々追われる。ここでは河口の留網に入ったサケ約800匹を一旦上げたら採卵、採卵が終わったらまた800匹毎上げる。それを繰り返しながら一日の作業を終える。そんな番屋での楽しみはやはり食事だ。食卓には賄いの女性が作った料理が朝、昼、晩並ぶ。普段口数の少ない現場の男たちもこの時ばかりは会話も弾む。時折り食卓に並ぶ。ここでは若い人もいるが50代~60代の人たちが中心に働いている。24時間体制で番屋は動いているが現在の宿泊は2人ずつの交代で行う。また番屋から少し離れた所に密漁を監視する小屋もあり、こちらには3人体制で寝泊まりしながら毎夜の監視を続けている。
又兵衛鍋とはどんな鍋?
いつ頃から食され、その名を誰が命名したのかは定かではないが、津軽石川鮭番屋には「又兵衛鍋」という変わった料理があると言う。近年は食生活のレベルも上がり年中美味しい物が溢れているため、番屋で鮭を処理した際に残る副産物を食べると言うことは少なくなったという。又兵衛鍋とは、そんな残った副産物をメイン食材とした料理らしい。使われるのは雌鮭から採卵した際に残る卵が入った卵巣の袋だ。これを良く洗い食べやすい大きさに切って、キャベツなどの野菜と一緒に炒め味噌やしょう油で味付けしたものだ。従って「鍋」という名は付いているが、ツユダクの鍋料理ではなくすき焼きのような炒め煮のような仕上げらしい。近年はもっぱら作られることは少なくなったが、かつて番屋で又兵衛鍋を食べたと言う人に聞くと「すき焼きなんか比にならないほど旨い。一回食ったらやめらない」と豪語する。家庭で鮭番屋料理・又兵衛鍋を再現するには、雌鮭を丸ごと一匹買い込んで腹を割り、ハラコを取り出し卵巣の袋を集めなければならない。当然ながら一匹から採れる量はたかが知れているから、鍋にするなら数匹分が必要となる。
ハラコご飯
宮古では鮭の卵である「イクラ」のことを「ハラコ(腹子)」と呼ぶ。大型の雌鮭からこぼれるハラコは別名・海のルビーとも呼ばれ冬の珍味の代表でもある。そんなハラコには塩としょう油の二種類の味付けがある。しょう油の味付けは同時に加える酒と相まってコクが増し、塩はハラコ本来が持つ濃厚な旨みを堪能できる。津軽石では断然「塩」の味付けが主流で、これを茶碗に盛った炊きたてご飯にかけたり、筋子のようにおにぎりの具として使う。